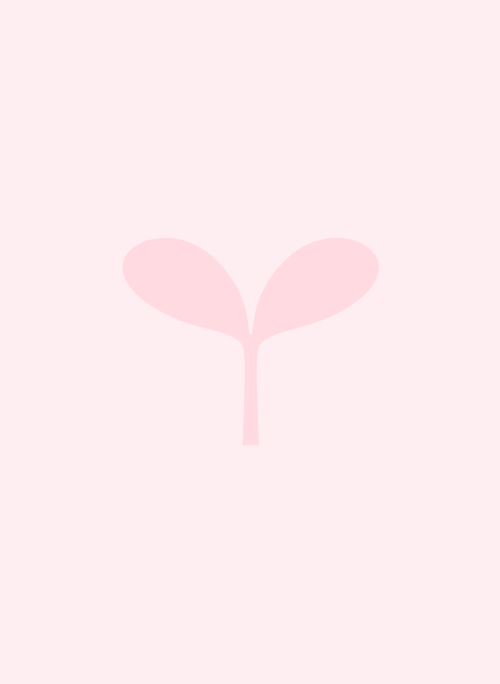では──
十一年前に親父の命で切腹させられた者たちというのは……
「幼い殿の供をしていた神崎帯刀の兄が切腹させられた理由は──これか」
事件の口封じのために……
「まあ、口封じと言うと身も蓋もないがな、
警護の任に当たっていながら、武士として主君を守りきれなかった者にとっては、やむを得ん処罰として儂が命じた」
親父殿がごりごりと顎を擦りながら言って、
「私には、当時も──そして未だに理解できませんが……
主君を目の前で賊に殺されておめおめと生きて返ってきたなど、武士にとっては恥なのでしょう?」
冷ややかに口にした青文に苦笑した。
「そして、主君を殺した賊を全て討ち滅ぼすのもまた──武士としては当然の道理と思いましたので」
武家社会の外で生まれ育った侍はそんな風に語った。
己には理解できないと言いながら、
理不尽に口封じを行ったわけではなく、
それは武家社会の道理にも適っている。
確かに、親父殿や藤岡たちが伊羽青文という人間に一目置いたのも頷ける。
「そして私は幕府を欺き、幼い殿が死んだという事実そのものをなかったことにした」
青文はそんな風に、驚くべき策謀を打ち明けた。
「私が注目したのは、末期養子として家督を継いで間もなかった真木瀬家の御子息は、まだ公方様へのお目見えを果たしていなかったという事実です。
顔が割れていないのであれば──殺害されたこと自体を隠蔽して、替え玉を用意すればいい。
その替え玉として、私が推挙した人間こそ、
当時数えで八つであり、殺された殿とは一つしか年の違わなかった──」
青文は可笑しそうにクスクスと笑って、
蝋燭の灯りの中で、白い指をこの俺へと突きつけた。
「──円士郎様、貴殿ですよ」
「はァっ!?」
十一年前に親父の命で切腹させられた者たちというのは……
「幼い殿の供をしていた神崎帯刀の兄が切腹させられた理由は──これか」
事件の口封じのために……
「まあ、口封じと言うと身も蓋もないがな、
警護の任に当たっていながら、武士として主君を守りきれなかった者にとっては、やむを得ん処罰として儂が命じた」
親父殿がごりごりと顎を擦りながら言って、
「私には、当時も──そして未だに理解できませんが……
主君を目の前で賊に殺されておめおめと生きて返ってきたなど、武士にとっては恥なのでしょう?」
冷ややかに口にした青文に苦笑した。
「そして、主君を殺した賊を全て討ち滅ぼすのもまた──武士としては当然の道理と思いましたので」
武家社会の外で生まれ育った侍はそんな風に語った。
己には理解できないと言いながら、
理不尽に口封じを行ったわけではなく、
それは武家社会の道理にも適っている。
確かに、親父殿や藤岡たちが伊羽青文という人間に一目置いたのも頷ける。
「そして私は幕府を欺き、幼い殿が死んだという事実そのものをなかったことにした」
青文はそんな風に、驚くべき策謀を打ち明けた。
「私が注目したのは、末期養子として家督を継いで間もなかった真木瀬家の御子息は、まだ公方様へのお目見えを果たしていなかったという事実です。
顔が割れていないのであれば──殺害されたこと自体を隠蔽して、替え玉を用意すればいい。
その替え玉として、私が推挙した人間こそ、
当時数えで八つであり、殺された殿とは一つしか年の違わなかった──」
青文は可笑しそうにクスクスと笑って、
蝋燭の灯りの中で、白い指をこの俺へと突きつけた。
「──円士郎様、貴殿ですよ」
「はァっ!?」