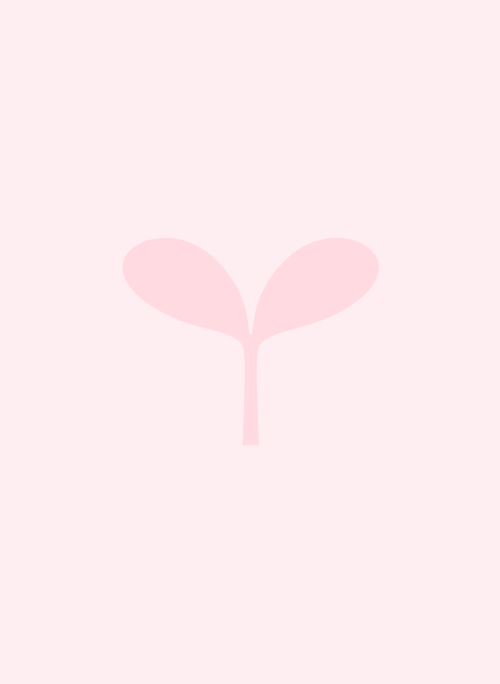「そんなの、また同じように末期養子を立ててれば良かったんじゃ……」
俺は言いかけたが、
「わずか九つの幼い殿にか?」
親父殿が言うのを聞いて、この方法には今度は無理があることに気づいた。
「良いか、末期養子の末期養子は認められておらんのだ」
更に親父殿はそう言って、
「先君の末期養子として幕府に届け出てあった幼い殿が危篤状態に陥っても──その殿に末期養子をとることはできん」
俺は生唾を飲み込んだ。
「じゃあ、十一年前にこの国が改易の危機に瀕したっていうのは──母上の兄が江戸で殺された事件じゃなくて、本当は……」
「そうだ。これが、この国が直面した本当の危機だ」
親父殿はそう言った。
「十五才の私はその話を、この屋敷の奥にあるあの座敷牢で耳にしました」
ここで青文が言って、黙って話を聞いていた冬馬が「座敷牢!?」と眉根を寄せた。
「ああ、私は心ない者どもに十五の年まで閉じこめられて育ったもので」
青文は自身の陰惨な過去をさらりと事も無げな口調でそう説明して、
だがそこに潜んだ皮肉げな響きから冬馬も何かを感じ取ったのか、それ以上は突っ込んで聞こうとはしなかった。
「話を聞いて──武家の仕組みや幕府が定めた諸法を知り、
私にはすぐに、どうすべきかの道がはっきりと見えた」
金髪の美青年は子供時代の出来事をそう語って、
道が──見えた──
俺は
留玖が子供の頃から、剣術の勝負で時々似たようなことを口にしていたのを思い出した。
どう刀を動かせば良いのかの道がはっきり見えるのだと。
頭脳か、
武芸か、
その違いはあるが、
同じように常人には見えぬものを見ていると言う二人を頭の中で比べて、
俺は、これが天才というものだろうかと思った。
俺は言いかけたが、
「わずか九つの幼い殿にか?」
親父殿が言うのを聞いて、この方法には今度は無理があることに気づいた。
「良いか、末期養子の末期養子は認められておらんのだ」
更に親父殿はそう言って、
「先君の末期養子として幕府に届け出てあった幼い殿が危篤状態に陥っても──その殿に末期養子をとることはできん」
俺は生唾を飲み込んだ。
「じゃあ、十一年前にこの国が改易の危機に瀕したっていうのは──母上の兄が江戸で殺された事件じゃなくて、本当は……」
「そうだ。これが、この国が直面した本当の危機だ」
親父殿はそう言った。
「十五才の私はその話を、この屋敷の奥にあるあの座敷牢で耳にしました」
ここで青文が言って、黙って話を聞いていた冬馬が「座敷牢!?」と眉根を寄せた。
「ああ、私は心ない者どもに十五の年まで閉じこめられて育ったもので」
青文は自身の陰惨な過去をさらりと事も無げな口調でそう説明して、
だがそこに潜んだ皮肉げな響きから冬馬も何かを感じ取ったのか、それ以上は突っ込んで聞こうとはしなかった。
「話を聞いて──武家の仕組みや幕府が定めた諸法を知り、
私にはすぐに、どうすべきかの道がはっきりと見えた」
金髪の美青年は子供時代の出来事をそう語って、
道が──見えた──
俺は
留玖が子供の頃から、剣術の勝負で時々似たようなことを口にしていたのを思い出した。
どう刀を動かせば良いのかの道がはっきり見えるのだと。
頭脳か、
武芸か、
その違いはあるが、
同じように常人には見えぬものを見ていると言う二人を頭の中で比べて、
俺は、これが天才というものだろうかと思った。