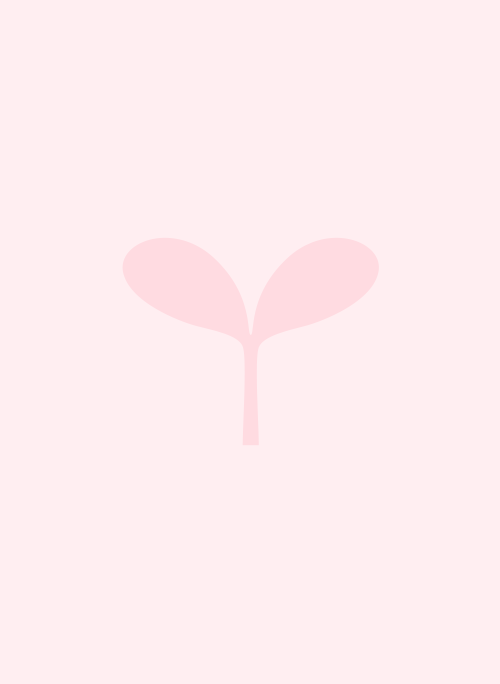俺はそう語る冬馬から、親父殿へと視線を移した。
「お前には伏せてあったがな」
親父殿は頷いて、ごりごりと顎を擦った。
「こたびのことで、冬馬がお前にこれ以上このことを隠すことはできない、
何としても伝えたいと申すのでな。
ここに連れて参った」
親父殿はそう言って、俺の知らない冬馬の過去を語った。
「十一年前、闇鴉の六郎太を斬った儂は、親を失って残された子供を自分の子とした。
もっとも──
夜叉之助と羅刹丸──二人の兄弟のうち兄の夜叉之助は、目の前で親を斬り殺された恨みを抱いたまま姿を消し、
どうやら今になって、復讐に戻ってきた様子だがな」
「冬馬、お前は──親を目の前で殺されて──なのに、その仇の子になったのか?」
俺は信じられない思いで、からからに干上がった喉から掠れた声を出した。
これまで冬馬が俺や親父殿に向けてきた目の中に、夜叉之助のもののような恨みや憎悪の色は感じられなかった。
「私は──実の父である闇鴉の六郎太に、一度として愛情など感じたことはありません。
あの賊は、私や夜叉之助のことなど、自分の道具としか思っていなかった。
幼い子供の我々にまで、盗賊の仕事をさせていたのです。
しくじれば
なじられ、
殴られ、
斬りつけられ──
私はずっと、いつ殺されるかも知れない恐怖の中で生きていた。
だから、父親が目の前で殺されるのを見ても、私は何も感じませんでした。
ただ、これまでの悪行に対する当然の報いだと──そう思っただけでした。
晴蔵様が、望むならば人の子としての生活を与えようと手を差し伸べてくださった時、私はこれで地獄のような世界から抜け出せると、夢中でその手をとった……
私はあの男も……兄の夜叉之助もそうだろうと、思いこんでいましたが──」
「お前には伏せてあったがな」
親父殿は頷いて、ごりごりと顎を擦った。
「こたびのことで、冬馬がお前にこれ以上このことを隠すことはできない、
何としても伝えたいと申すのでな。
ここに連れて参った」
親父殿はそう言って、俺の知らない冬馬の過去を語った。
「十一年前、闇鴉の六郎太を斬った儂は、親を失って残された子供を自分の子とした。
もっとも──
夜叉之助と羅刹丸──二人の兄弟のうち兄の夜叉之助は、目の前で親を斬り殺された恨みを抱いたまま姿を消し、
どうやら今になって、復讐に戻ってきた様子だがな」
「冬馬、お前は──親を目の前で殺されて──なのに、その仇の子になったのか?」
俺は信じられない思いで、からからに干上がった喉から掠れた声を出した。
これまで冬馬が俺や親父殿に向けてきた目の中に、夜叉之助のもののような恨みや憎悪の色は感じられなかった。
「私は──実の父である闇鴉の六郎太に、一度として愛情など感じたことはありません。
あの賊は、私や夜叉之助のことなど、自分の道具としか思っていなかった。
幼い子供の我々にまで、盗賊の仕事をさせていたのです。
しくじれば
なじられ、
殴られ、
斬りつけられ──
私はずっと、いつ殺されるかも知れない恐怖の中で生きていた。
だから、父親が目の前で殺されるのを見ても、私は何も感じませんでした。
ただ、これまでの悪行に対する当然の報いだと──そう思っただけでした。
晴蔵様が、望むならば人の子としての生活を与えようと手を差し伸べてくださった時、私はこれで地獄のような世界から抜け出せると、夢中でその手をとった……
私はあの男も……兄の夜叉之助もそうだろうと、思いこんでいましたが──」