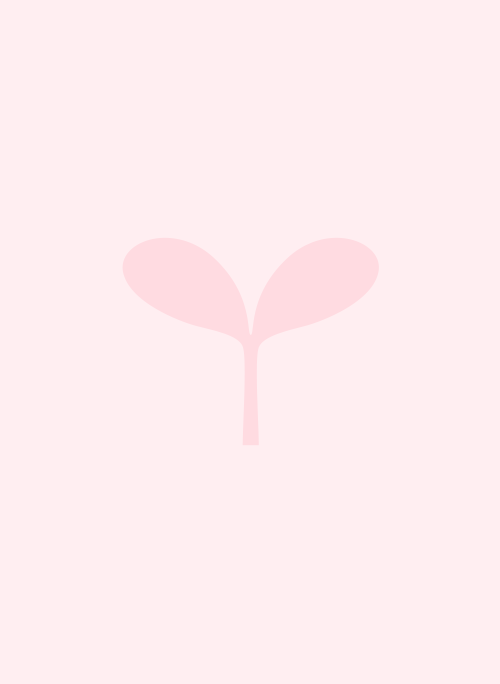顔をしかめてこちらを覗き込んでいる鬼之介と目が合って、
「駄目だな、俺は」
俺は力無く笑った。
「彼女のことを、誰より認めているつもりだったのにな。
あんな野郎に言われた一言で──留玖に嫉妬した」
「嫉妬か」
鬼之介は薄く雪の積もった塀の上を眺めた。
「まあ、それは当然だな。武芸者ならば、あれは誰でも嫉妬する才能だ」
鬼之介はそれから俺に視線を戻して軽く睨んだ。
「貴様、だからと言って彼女につらく当たるな」
「……わかってるよ」
留玖は何も悪くない。
なのに俺は、
俺を慕ってくれる彼女に、あんな態度をとった……。
更に自己嫌悪に陥って俺は下を向いて、鬼之介は何やら小さく笑い声を立てた。
「なんだ。貴様も嫉妬はするのか」
「……あんなあからさまに、虹庵先生も留玖を認めてるって態度とるのを見たらな」
「なら、まだ見込みはあるってことじゃないのか」
「…………?」
鬼之介が何を言い出したのかわからず、俺は相変わらず血色の悪い顔を見上げた。
「留玖殿を認めていると言えば聞こえはいいが──どうもこのところの貴様は、彼女より自分が劣ると完全に諦めているように見えていたからな」
鬼之介は立ったまま、俺の横の壁に背を預けて、
「武士が嫉妬などとみっともないかもしれんがな、悔しさも嫉妬も覚えなくなったら、もう勝てん」
と言った。
「駄目だな、俺は」
俺は力無く笑った。
「彼女のことを、誰より認めているつもりだったのにな。
あんな野郎に言われた一言で──留玖に嫉妬した」
「嫉妬か」
鬼之介は薄く雪の積もった塀の上を眺めた。
「まあ、それは当然だな。武芸者ならば、あれは誰でも嫉妬する才能だ」
鬼之介はそれから俺に視線を戻して軽く睨んだ。
「貴様、だからと言って彼女につらく当たるな」
「……わかってるよ」
留玖は何も悪くない。
なのに俺は、
俺を慕ってくれる彼女に、あんな態度をとった……。
更に自己嫌悪に陥って俺は下を向いて、鬼之介は何やら小さく笑い声を立てた。
「なんだ。貴様も嫉妬はするのか」
「……あんなあからさまに、虹庵先生も留玖を認めてるって態度とるのを見たらな」
「なら、まだ見込みはあるってことじゃないのか」
「…………?」
鬼之介が何を言い出したのかわからず、俺は相変わらず血色の悪い顔を見上げた。
「留玖殿を認めていると言えば聞こえはいいが──どうもこのところの貴様は、彼女より自分が劣ると完全に諦めているように見えていたからな」
鬼之介は立ったまま、俺の横の壁に背を預けて、
「武士が嫉妬などとみっともないかもしれんがな、悔しさも嫉妬も覚えなくなったら、もう勝てん」
と言った。