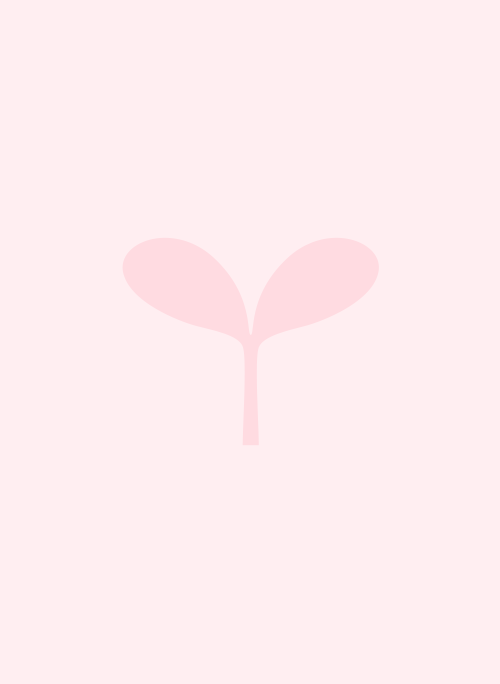俺は幼い頃から留玖の才能を誰より近くで見続けてきたし、だからこそ認めてきた。
ずっと、そう思ってきた。
しかし清十郎の言葉は、取り繕った俺の心の外側を剥ぎ取って、
彼女を認め、大切に思う心によって押さえつけてずっと隠してきた、留玖の才能に対する激しい嫉妬心と羨望、そして焦りを再び俺の前に引きずり出した。
どんなに留玖を認め、大切に思っても──
あんな風にはっきり、留玖より劣ると嘲笑われたことは屈辱だった。
彼女が女だからとか
農民の出だからとか
侮るつもりはない。
それでも、
例え留玖が男で、
生粋の武家の生まれだったとしても、
俺は──武芸の家である結城家の長子だ。
この誇りと、
誰にも負けたくない。
そんな思いとが、
今さらのように、忘れかけていた留玖に対する劣等感を呼び覚まして、憎しみにも似た感情が胸の中で渦を巻いた。
更に、
幼い頃にも抱いたそれらの感情に加えて、
留玖が自分の惚れた女だということが、新たな焦りを生んでいた。
どうしても、
彼女を守りたい。
そのために彼女より強くありたいと、そう思ってしまう。
「おい……!」
道場の裏で、壁に背を預けて座り込んでいたら、頭上から鬼之介の声が降ってきた。
ずっと、そう思ってきた。
しかし清十郎の言葉は、取り繕った俺の心の外側を剥ぎ取って、
彼女を認め、大切に思う心によって押さえつけてずっと隠してきた、留玖の才能に対する激しい嫉妬心と羨望、そして焦りを再び俺の前に引きずり出した。
どんなに留玖を認め、大切に思っても──
あんな風にはっきり、留玖より劣ると嘲笑われたことは屈辱だった。
彼女が女だからとか
農民の出だからとか
侮るつもりはない。
それでも、
例え留玖が男で、
生粋の武家の生まれだったとしても、
俺は──武芸の家である結城家の長子だ。
この誇りと、
誰にも負けたくない。
そんな思いとが、
今さらのように、忘れかけていた留玖に対する劣等感を呼び覚まして、憎しみにも似た感情が胸の中で渦を巻いた。
更に、
幼い頃にも抱いたそれらの感情に加えて、
留玖が自分の惚れた女だということが、新たな焦りを生んでいた。
どうしても、
彼女を守りたい。
そのために彼女より強くありたいと、そう思ってしまう。
「おい……!」
道場の裏で、壁に背を預けて座り込んでいたら、頭上から鬼之介の声が降ってきた。