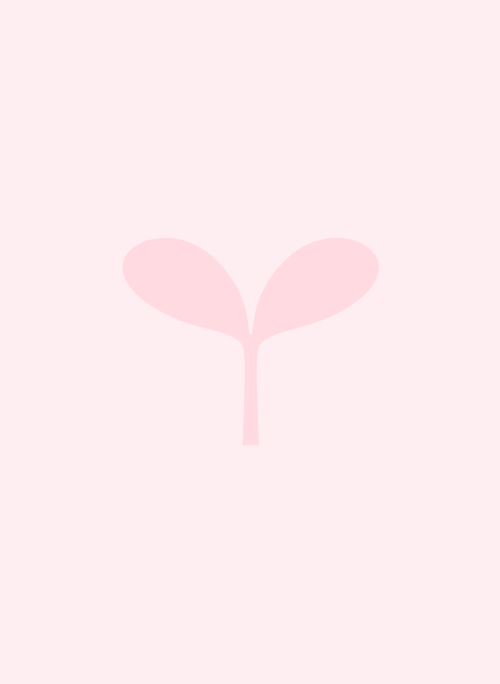【円】
正直、見ていて背筋が粟立った。
留玖がどうして強いのか。
自分がどうして彼女に勝てないのか。
彼女の才能の片鱗を垣間見た気がした。
以前、虹庵が留玖に火箸で打ちかかり、それを彼女がキセルで防いだ時の、二人の動きが思い起こされる。
虹庵は火箸を明かな武器として扱い、留玖もまたキセルを武器として使った。
その武芸者たる者の戦い方を、今の試合は物語っていた。
留玖は、刃引き刀を──
試合のための道具ではなく、
火箸やキセルと同様に、相手を殺すための「武器として」使ったのだ。
それは俺や鬼之介、清十郎にはできない戦い方だった。
彼女はおそらく──手元にある武器がかんざし一本だったとしても、瞬時に刀を相手に戦う術を編み出すのだろう。
本能のように。
刃引き刀という同じ武器を手にしていながら、まるで──
清十郎は試合のつもりで木刀を握っているのに、
留玖は真剣を手にして戦っているかのような印象だった。
清十郎はさぞかし戦いづらかったことだろう。
「とんでもない使い手だな、彼女は」
鬼之介が、ごくりと喉を鳴らして小さく呟いた。
彼にも、今の試合がどういうものだったのか理解できたようだ。
直接刃を交えた清十郎ももちろん気づいているだろう。
俺は周囲の野次馬たちを見回してそっと苦笑した。
さて、この場で試合を見物していた者の中に、果たして勝敗を分けた両者のこの違いに気づけた者が何人いたのか──。