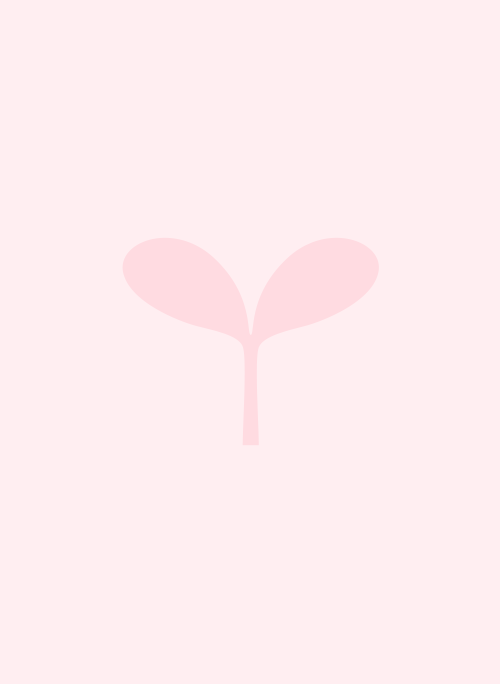冷静さを失った私は滅茶苦茶に暴れて、清十郎の胸を叩いたけれど、そんなことでは男の人の力には抵抗できなくて、
「離して!」
泣き叫ぶ私の手を捕まえたまま、清十郎は雪の中でこちらをじっと見つめた。
「お前も、親の愛情に飢えて育ったんだろう」
そう呟いた清十郎の氷のような瞳には、
憎しみとも怒りともつかぬ冷たい炎のようなものがちろちろと見え隠れしていて──
──誰かの、目に似てる。
どうしてそう思ったのかわからないけれど、
私は、これと同じ目を知っている気がした。
「なのに、どうしてお前はそんな風でいられる?」
清十郎が線の細い整った顔を近づけてくる。
「いやっ」
私は必死に逃げようとして、
「結城円士郎は、お前を裏切ったんだぞ」
彼の言葉に凍りついた。
「ち……違うもん……エンは……」
何とか弱々しく首を振った私に、
「かわいそうにな、留玖。
お前はまた、信じていた者に裏切られて捨てられた」
残酷な清十郎の言葉が突き刺さった。
「離して!」
泣き叫ぶ私の手を捕まえたまま、清十郎は雪の中でこちらをじっと見つめた。
「お前も、親の愛情に飢えて育ったんだろう」
そう呟いた清十郎の氷のような瞳には、
憎しみとも怒りともつかぬ冷たい炎のようなものがちろちろと見え隠れしていて──
──誰かの、目に似てる。
どうしてそう思ったのかわからないけれど、
私は、これと同じ目を知っている気がした。
「なのに、どうしてお前はそんな風でいられる?」
清十郎が線の細い整った顔を近づけてくる。
「いやっ」
私は必死に逃げようとして、
「結城円士郎は、お前を裏切ったんだぞ」
彼の言葉に凍りついた。
「ち……違うもん……エンは……」
何とか弱々しく首を振った私に、
「かわいそうにな、留玖。
お前はまた、信じていた者に裏切られて捨てられた」
残酷な清十郎の言葉が突き刺さった。