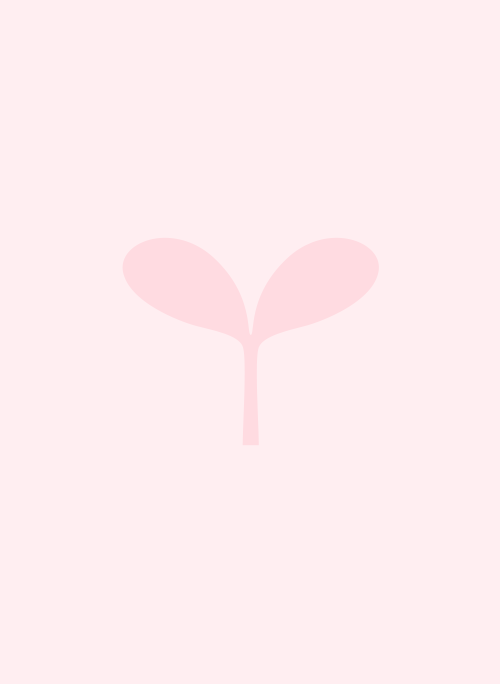「馬鹿野郎──っ!!」
怒声で目を開けたら、
追いついた円士郎が素手で刃を握って、脇差しを止めていた。
月明かりの下で、ぽたぽたと円士郎の手からどす黒い血がしたたっていて、
凍りついた私の手に、円士郎は続けて手刀を叩き込んで刀を落として、怪我をした手で構わずに私の腕をつかんだ。
「お前──何やってんだ留玖っ」
ぬるっとした感触が腕から伝わってくる。
「……エン……手が……」
呟いた私を力任せに抱き寄せて、円士郎は凄い力で私をかき抱いて、
「なんで──なんで──こんな、馬鹿な真似を──」
円士郎の声と体は、さっきの何倍も震えていた。
「だって……!」
涙がとめどもなく溢れ続けた。
「だって、私がエンをあんな目に遭わせたんだよ!
私のせいで、エンは──」
「違う!!」
円士郎が叫んだ。
「違うだろうが! 何言ってんだ留玖!
おひさって奴にそう吹き込まれたのか!? そんな言葉、真に受けんなよ!」
円士郎は私の両肩をつかんで、私の目を真っ直ぐ見つめた。
「そいつが風佳にやらせたんだろうが! お前のせいじゃねえ! 絶対に違う!! だから、こんな真似──」
円士郎の顔が歪んだ。
「こんな真似、すんなよ──」
怒声で目を開けたら、
追いついた円士郎が素手で刃を握って、脇差しを止めていた。
月明かりの下で、ぽたぽたと円士郎の手からどす黒い血がしたたっていて、
凍りついた私の手に、円士郎は続けて手刀を叩き込んで刀を落として、怪我をした手で構わずに私の腕をつかんだ。
「お前──何やってんだ留玖っ」
ぬるっとした感触が腕から伝わってくる。
「……エン……手が……」
呟いた私を力任せに抱き寄せて、円士郎は凄い力で私をかき抱いて、
「なんで──なんで──こんな、馬鹿な真似を──」
円士郎の声と体は、さっきの何倍も震えていた。
「だって……!」
涙がとめどもなく溢れ続けた。
「だって、私がエンをあんな目に遭わせたんだよ!
私のせいで、エンは──」
「違う!!」
円士郎が叫んだ。
「違うだろうが! 何言ってんだ留玖!
おひさって奴にそう吹き込まれたのか!? そんな言葉、真に受けんなよ!」
円士郎は私の両肩をつかんで、私の目を真っ直ぐ見つめた。
「そいつが風佳にやらせたんだろうが! お前のせいじゃねえ! 絶対に違う!! だから、こんな真似──」
円士郎の顔が歪んだ。
「こんな真似、すんなよ──」