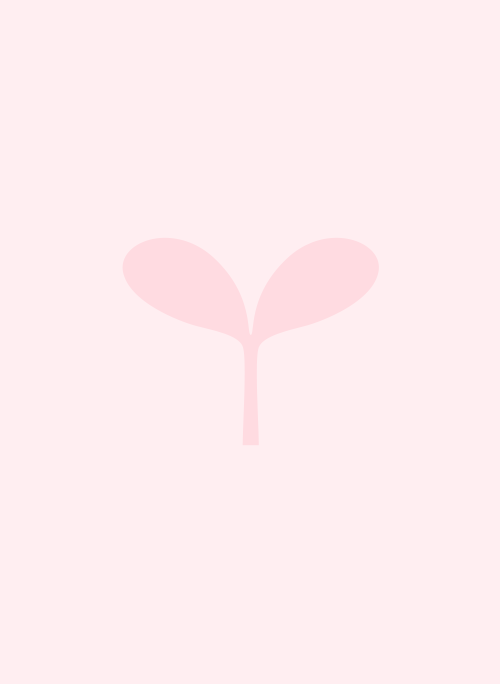「俺は、国の政治だの何だのって、自分とは関係ねえ遠い世界のことだと考えてたけど──」
円士郎が口にした内容は、私も昼間考えていたことだったので、びっくりした。
「そうじゃねえって、お前の姿見て知った。
城の中の奴らがやってる役目だってよ、きっとこのまま家督を継いでたら、俺はただの仕事だとしか思わなかった。
お前みたいに泣いたり悲しんだりする奴がいるってことは、見えねえままだったよ」
「わ……私も、同じことを知ったよ。
青文様が失脚して、こんな風に村の人の命が関係してくるなんて、思わなかった」
円士郎は「そうか」と私を見つめて微笑んで、
「なあ、留玖。お前はさ、農民の子なんかに生まれてこなければ良かったって言ったけどよ……俺は、お前がこの村に生まれて、こうして俺と出会ってくれたのにはやっぱり意味があると思うぜ」
そんなことを言って、円士郎の両手が私の頬を包み込んで、顔を上に向けて、
彼の顔が近づいて、優しく唇が重なって、
「ずっと俺のそばにいろよ、留玖」
円士郎はどきどきするような声で、そう囁いてくれたけれど──
──円士郎様が死にかけたのは、みぃ~んなあんたのせい。
冷たい氷のようなおひさの言葉が蘇って、私の心臓から温かいどきどきを消し去った。
「留玖……?」
私はうつむいて、円士郎から一歩離れた。
私には彼のそばにいる資格なんてないんだ、と思った。
円士郎が口にした内容は、私も昼間考えていたことだったので、びっくりした。
「そうじゃねえって、お前の姿見て知った。
城の中の奴らがやってる役目だってよ、きっとこのまま家督を継いでたら、俺はただの仕事だとしか思わなかった。
お前みたいに泣いたり悲しんだりする奴がいるってことは、見えねえままだったよ」
「わ……私も、同じことを知ったよ。
青文様が失脚して、こんな風に村の人の命が関係してくるなんて、思わなかった」
円士郎は「そうか」と私を見つめて微笑んで、
「なあ、留玖。お前はさ、農民の子なんかに生まれてこなければ良かったって言ったけどよ……俺は、お前がこの村に生まれて、こうして俺と出会ってくれたのにはやっぱり意味があると思うぜ」
そんなことを言って、円士郎の両手が私の頬を包み込んで、顔を上に向けて、
彼の顔が近づいて、優しく唇が重なって、
「ずっと俺のそばにいろよ、留玖」
円士郎はどきどきするような声で、そう囁いてくれたけれど──
──円士郎様が死にかけたのは、みぃ~んなあんたのせい。
冷たい氷のようなおひさの言葉が蘇って、私の心臓から温かいどきどきを消し去った。
「留玖……?」
私はうつむいて、円士郎から一歩離れた。
私には彼のそばにいる資格なんてないんだ、と思った。