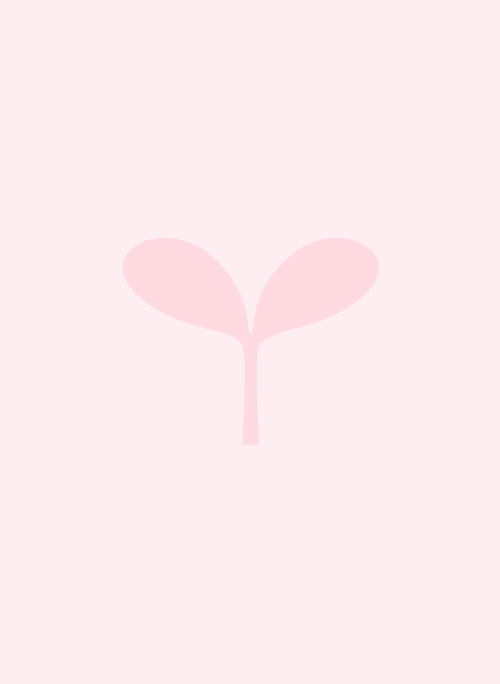善政を布いていたという青文が失脚したことで、実際にこの国にどんな影響があるのかについては
私はあまり考えていなくて、
何か影響があるとしても自分とは関係のない遠い政治の世界の話のような気がしていた。
しかしすぐに、全く思いも寄らない形でそれは私の前に現れることになった。
数日後、用があって町に出かけた私は、
「おつるぎ様」
と、通りの真ん中で、背後から声をかけられた。
振り向いた先に立って微笑んでいたのは意外な人物だった。
「おひさちゃん!?」
人混みの中に、あの事件以来行方不明になっていた女中の姿を認めて、私は思わず声を上げた。
「今までどこにいたの!? みんな探して──」
「私を捕らえるためにね。ふふふ……そんなに簡単に捕まったりしないわ」
おひさは、相変わらず朗らかに笑ってそう言って──けれど私を見つめる目つきは、どこか見下したような、小馬鹿にしたような冷たいものだった。
「ざぁんねん。円士郎様、ぴんぴんしているんですってね。
おつるぎ様、あんたのお友達のあの大河家のお嬢さん、とんでもない根性なしだわ。ちゃんと致死量ぎりぎりまで飲ませるように言い聞かせておいたのに」
「な……なんで……」
おひさの口から放たれた信じられない言葉の羅列に、私はぞっとした。
「なんで……おひさちゃんが、風佳にそんなこと……」
あははは! と、木枯らしの吹く冷たい曇り空の下でおひさは哄笑を上げた。
屋敷にいた頃の無邪気な笑い方と同じだったけれど、今はそれがひどく残虐で悪意に満ちた表情のように感じられた。
「そうね。あたしは別に結城家にも、円士郎様にも恨みはないわ。理由は──あんたよ、おつるぎ様」
「わ……わたし?」
びっくりして目を丸くする私に、おひさは獲物をいたぶるような残酷な笑顔を向けた。
「そうよ、おつるぎ様。愛しい愛しい円士郎様が死にかけたのは、みぃ~んなあんたのせい」
私はあまり考えていなくて、
何か影響があるとしても自分とは関係のない遠い政治の世界の話のような気がしていた。
しかしすぐに、全く思いも寄らない形でそれは私の前に現れることになった。
数日後、用があって町に出かけた私は、
「おつるぎ様」
と、通りの真ん中で、背後から声をかけられた。
振り向いた先に立って微笑んでいたのは意外な人物だった。
「おひさちゃん!?」
人混みの中に、あの事件以来行方不明になっていた女中の姿を認めて、私は思わず声を上げた。
「今までどこにいたの!? みんな探して──」
「私を捕らえるためにね。ふふふ……そんなに簡単に捕まったりしないわ」
おひさは、相変わらず朗らかに笑ってそう言って──けれど私を見つめる目つきは、どこか見下したような、小馬鹿にしたような冷たいものだった。
「ざぁんねん。円士郎様、ぴんぴんしているんですってね。
おつるぎ様、あんたのお友達のあの大河家のお嬢さん、とんでもない根性なしだわ。ちゃんと致死量ぎりぎりまで飲ませるように言い聞かせておいたのに」
「な……なんで……」
おひさの口から放たれた信じられない言葉の羅列に、私はぞっとした。
「なんで……おひさちゃんが、風佳にそんなこと……」
あははは! と、木枯らしの吹く冷たい曇り空の下でおひさは哄笑を上げた。
屋敷にいた頃の無邪気な笑い方と同じだったけれど、今はそれがひどく残虐で悪意に満ちた表情のように感じられた。
「そうね。あたしは別に結城家にも、円士郎様にも恨みはないわ。理由は──あんたよ、おつるぎ様」
「わ……わたし?」
びっくりして目を丸くする私に、おひさは獲物をいたぶるような残酷な笑顔を向けた。
「そうよ、おつるぎ様。愛しい愛しい円士郎様が死にかけたのは、みぃ~んなあんたのせい」