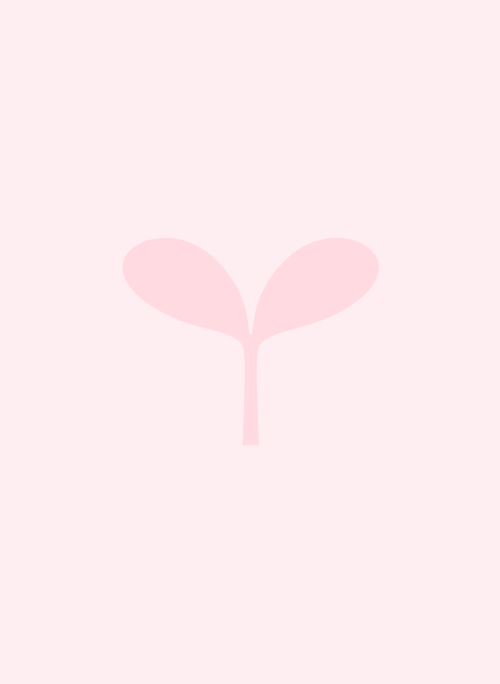次の日は雨で、
俺は開け放った障子の向こうに煙る庭を、床(とこ)に座って眺めていた。
剣術を通してこれまで学んできたものは刀を振るう技術だけか
耳の奥には、昨晩親父殿に言われた言葉がこびりついている。
俺が剣術で学んできたこと──って何だ?
見ているだけで気が滅入りそうになる秋の雨を睨んで、
「こいつは無事で何より」
庭からかかった声でそちらに視線を向けると、
憂鬱な雨の中を、赤い唐傘を差した着流し姿の金髪の男が歩いてくるところだった。
「青文……」
「今は遊水だ」
そう言って、
青文──いや本人曰く遊水か──は傘をたたみ、庭に面した俺の部屋の前の廊下に勝手に座って、
彼の名を呼び間違えた俺を見た。
「なんだ。命が助かったと聞いて来てみれば、随分とフヌケたツラしてやがるな」
「……うるせーよ」
ふふん、と遊水は鼻を鳴らした。
「許嫁の娘に殺されかけたことがそんなに衝撃的だったかい?」
俺は黙った。
遊水はそんな俺をじっと見つめて、
「──というだけでもなさそうだな」
お得意の能力で何かを読みとったのか、そんな風に言った。
俺は開け放った障子の向こうに煙る庭を、床(とこ)に座って眺めていた。
剣術を通してこれまで学んできたものは刀を振るう技術だけか
耳の奥には、昨晩親父殿に言われた言葉がこびりついている。
俺が剣術で学んできたこと──って何だ?
見ているだけで気が滅入りそうになる秋の雨を睨んで、
「こいつは無事で何より」
庭からかかった声でそちらに視線を向けると、
憂鬱な雨の中を、赤い唐傘を差した着流し姿の金髪の男が歩いてくるところだった。
「青文……」
「今は遊水だ」
そう言って、
青文──いや本人曰く遊水か──は傘をたたみ、庭に面した俺の部屋の前の廊下に勝手に座って、
彼の名を呼び間違えた俺を見た。
「なんだ。命が助かったと聞いて来てみれば、随分とフヌケたツラしてやがるな」
「……うるせーよ」
ふふん、と遊水は鼻を鳴らした。
「許嫁の娘に殺されかけたことがそんなに衝撃的だったかい?」
俺は黙った。
遊水はそんな俺をじっと見つめて、
「──というだけでもなさそうだな」
お得意の能力で何かを読みとったのか、そんな風に言った。