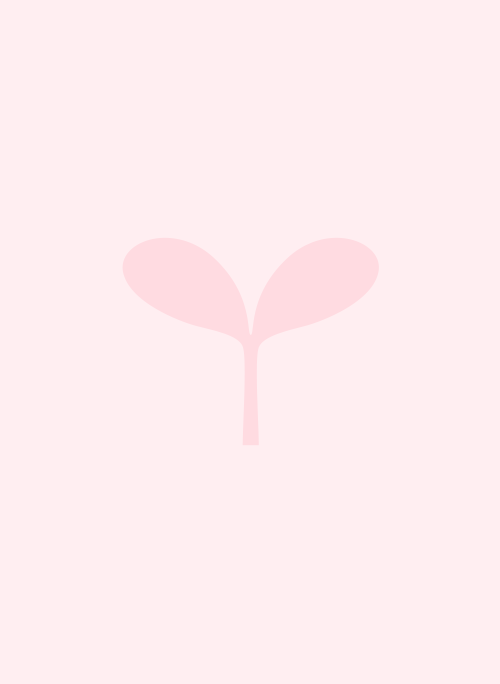「お前もこのような愚か者を気にかける必要などない。放っておけ。
留守の間にどれだけ腕を上げたか、明日は道場で見てやろう」
「────」
親父殿の言葉に、俺は奥歯を噛みしめて、
「そんな……父上、それはあまりに……!」
留玖のか細い声が襖の向こうから聞こえた。
ふとんの上に投げ出した両手に視線を落とした俺を一瞥して、親父殿は立ち上がった。
「見苦しいぞ。それでも武士か。
円士郎、確かに今の貴様には家督も道場も継がせることはできん」
そんな言葉を残して、親父殿は部屋を出ていった。
襖の向こうに、俺にかける言葉を探しているように留玖の気配が残って、
しかし言うべき内容が見つからなかったのか、やがてその気配も消えた。
一人になって、
打ちひしがれたまま、親父殿に言われたことを胸の中で繰り返して、
無様にうろたえて
情けない
「確かに──情けねえよな……」
くそっ!
俺は鉛のような手で、畳を殴った。
留守の間にどれだけ腕を上げたか、明日は道場で見てやろう」
「────」
親父殿の言葉に、俺は奥歯を噛みしめて、
「そんな……父上、それはあまりに……!」
留玖のか細い声が襖の向こうから聞こえた。
ふとんの上に投げ出した両手に視線を落とした俺を一瞥して、親父殿は立ち上がった。
「見苦しいぞ。それでも武士か。
円士郎、確かに今の貴様には家督も道場も継がせることはできん」
そんな言葉を残して、親父殿は部屋を出ていった。
襖の向こうに、俺にかける言葉を探しているように留玖の気配が残って、
しかし言うべき内容が見つからなかったのか、やがてその気配も消えた。
一人になって、
打ちひしがれたまま、親父殿に言われたことを胸の中で繰り返して、
無様にうろたえて
情けない
「確かに──情けねえよな……」
くそっ!
俺は鉛のような手で、畳を殴った。