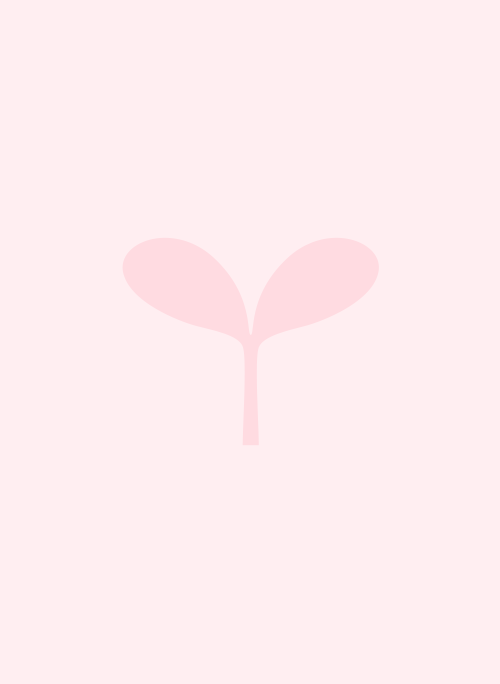「ほう」
俺の話を聞いた親父殿は、全く動じずに顎を擦った。
「毒芹の毒か。前に伊羽家の座敷牢でも、死にきれなかった者の成れの果てを見たが……確かに重い後遺症が残るようだな」
「なに──?」
春先に伊羽家を訪れた時のおぞましい光景を思い出して、俺はぞっとした。
青文が実の父親を暗殺するのに用いて、ためらい、量を加減して殺しきれなかったという毒──
あれが、毒芹の毒──?
「両手が動かぬ程度ならば、お前はまだ運が良かったというところだろう」
平然と言い放った親父殿を見て、一気に頭に血が上った。
「運が良かった!? 有り難がれって言うのか!?
冗談じゃねえぞ! 剣が握れなくなったら──俺はどうなる!? 晴蔵の名や、道場は──」
「継げまいな。留玖か、宮川か──才のある者に継がせることになろう」
「────結城家の家督は……」
「さて。少なくとも、不自由な腕で殿の剣術指南は務まらんだろうな」
「────」
淡々とした口調で容赦のない現実を突きつけられて、
俺は絶句し、震えながら自分の両手を見下ろした。
生まれて初めて、どん底に突き落とされる恐怖を味わった。
「情けないな、円士郎」
そんな俺に冷たい視線を向けて、親父殿は突き放すように言った。
「無様にうろたえて。何だそのザマは。
貴様、剣術を通してこれまで学んできたものは刀を振るう技術だけか」
鋭い眼光で睨み据えられて、俺は一言も発することができずに親父殿の顔を見つめた。
「日頃の威勢はどうした? これまで威張り散らして己を誇示してきて、剣の道が絶たれるとわかればそれか」
親父殿は俺から視線を移して、部屋の奥の襖を見た。
「留玖! そこにおるのだろう」
親父殿は襖の向こうにそう声をかけて、
「……はい……」
少女の小さな声がした。
俺の話を聞いた親父殿は、全く動じずに顎を擦った。
「毒芹の毒か。前に伊羽家の座敷牢でも、死にきれなかった者の成れの果てを見たが……確かに重い後遺症が残るようだな」
「なに──?」
春先に伊羽家を訪れた時のおぞましい光景を思い出して、俺はぞっとした。
青文が実の父親を暗殺するのに用いて、ためらい、量を加減して殺しきれなかったという毒──
あれが、毒芹の毒──?
「両手が動かぬ程度ならば、お前はまだ運が良かったというところだろう」
平然と言い放った親父殿を見て、一気に頭に血が上った。
「運が良かった!? 有り難がれって言うのか!?
冗談じゃねえぞ! 剣が握れなくなったら──俺はどうなる!? 晴蔵の名や、道場は──」
「継げまいな。留玖か、宮川か──才のある者に継がせることになろう」
「────結城家の家督は……」
「さて。少なくとも、不自由な腕で殿の剣術指南は務まらんだろうな」
「────」
淡々とした口調で容赦のない現実を突きつけられて、
俺は絶句し、震えながら自分の両手を見下ろした。
生まれて初めて、どん底に突き落とされる恐怖を味わった。
「情けないな、円士郎」
そんな俺に冷たい視線を向けて、親父殿は突き放すように言った。
「無様にうろたえて。何だそのザマは。
貴様、剣術を通してこれまで学んできたものは刀を振るう技術だけか」
鋭い眼光で睨み据えられて、俺は一言も発することができずに親父殿の顔を見つめた。
「日頃の威勢はどうした? これまで威張り散らして己を誇示してきて、剣の道が絶たれるとわかればそれか」
親父殿は俺から視線を移して、部屋の奥の襖を見た。
「留玖! そこにおるのだろう」
親父殿は襖の向こうにそう声をかけて、
「……はい……」
少女の小さな声がした。