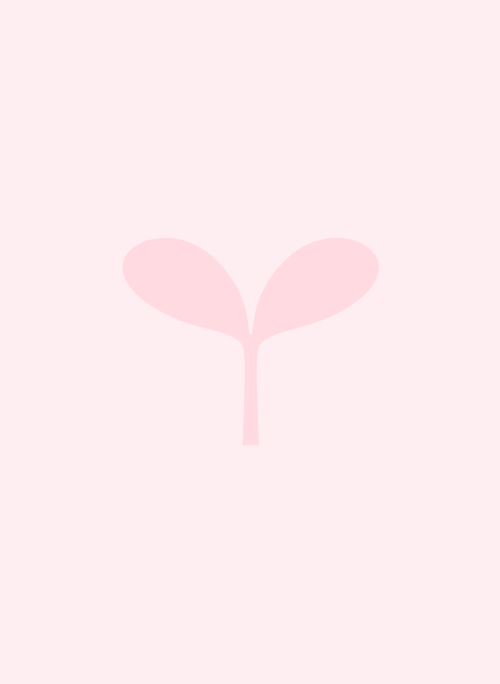「死なねえよ……。死ぬかよ、ばか」
円士郎が私の頭を撫でてくれる。
「お前を一人にして、死ねるわけねーだろうが」
その腕は悲しいくらい弱々しくて、私の目からは涙がこぼれ続けた。
「俺は平気だ、留玖」
円士郎の手が私のほっぺたを優しく撫でて、彼が微笑んだ。
「エン……」
「お前がせっかく縫ってくれた着物も……着ねーとな……」
語尾が消えて、私の頬から円士郎の手が滑り落ちた。
「エン!?」
私は悲鳴を上げた。
円士郎の体が力を失って、再びその目が硬く閉じられる。
「しっかりしてよ、エン……!」
私は泣きながら呼びかけたけれど、円士郎はもう瞼を開けてくれなくて──
それから
次の日もずっと、死んでしまったかのように眠り続けた。
私は片時もそばを離れたくなくて、ずっと円士郎の枕元にいた。
「姉上、私が代わりますから」
見かねた冬馬が部屋に戻るように言ってきたけれど、
「どうか少しはお休みください。これでは姉上まで倒れてしまいます」
「いや。エンのそばにいる」
私は頑なに拒んだ。
「部屋に戻ったって、エンがこんな状態なのに休めるわけなんかないよ……!」
円士郎が私の頭を撫でてくれる。
「お前を一人にして、死ねるわけねーだろうが」
その腕は悲しいくらい弱々しくて、私の目からは涙がこぼれ続けた。
「俺は平気だ、留玖」
円士郎の手が私のほっぺたを優しく撫でて、彼が微笑んだ。
「エン……」
「お前がせっかく縫ってくれた着物も……着ねーとな……」
語尾が消えて、私の頬から円士郎の手が滑り落ちた。
「エン!?」
私は悲鳴を上げた。
円士郎の体が力を失って、再びその目が硬く閉じられる。
「しっかりしてよ、エン……!」
私は泣きながら呼びかけたけれど、円士郎はもう瞼を開けてくれなくて──
それから
次の日もずっと、死んでしまったかのように眠り続けた。
私は片時もそばを離れたくなくて、ずっと円士郎の枕元にいた。
「姉上、私が代わりますから」
見かねた冬馬が部屋に戻るように言ってきたけれど、
「どうか少しはお休みください。これでは姉上まで倒れてしまいます」
「いや。エンのそばにいる」
私は頑なに拒んだ。
「部屋に戻ったって、エンがこんな状態なのに休めるわけなんかないよ……!」