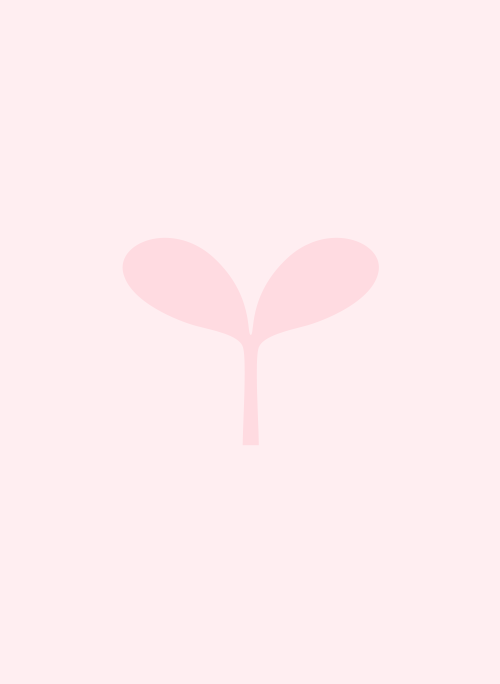「酷えって思うかもしれねえけど──俺だって納得してねえけどよ、でも──」
その日、優しく私の手を握ったまま、円士郎が言った言葉は、私の胸に突き刺さった。
「これが──戦国の世からずっと繰り返されてきた、武家の婚姻でもあるんだよ、留玖」
ようやく私は思い知ったのだった。
好きな人とは一緒になれないの?
いつか円士郎に向けて放った私のこの問いが、
いかにこの武家社会というものを知らない、愚かな娘の言葉であったのか──
初めて、
私が十二の歳で足を踏み入れたこの社会を、天下太平の世にありながら、まるで戦場(いくさば)のようだと思った。
その日、優しく私の手を握ったまま、円士郎が言った言葉は、私の胸に突き刺さった。
「これが──戦国の世からずっと繰り返されてきた、武家の婚姻でもあるんだよ、留玖」
ようやく私は思い知ったのだった。
好きな人とは一緒になれないの?
いつか円士郎に向けて放った私のこの問いが、
いかにこの武家社会というものを知らない、愚かな娘の言葉であったのか──
初めて、
私が十二の歳で足を踏み入れたこの社会を、天下太平の世にありながら、まるで戦場(いくさば)のようだと思った。