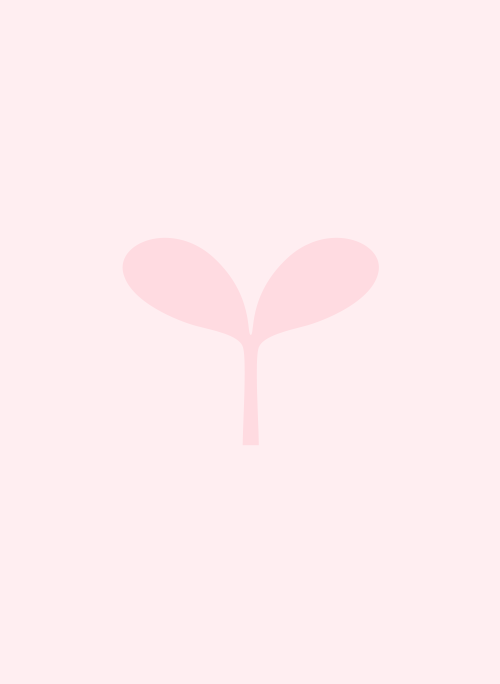「酷いよ……」
気づいたら、自然にそう漏らしてしまっていた。
「留玖……」
私のほうを向く円士郎の気配を感じながら、私は下を向いたまま、彼の袖をぎゅっとつかんだ。
以前、私は円士郎が信頼している人なら信頼できると言った。
けれど……わからなくなった。
「エンは──どうして、そんな酷いことを平然とするような冷たい人とつき合ってるの?」
震える声で尋ねた私の手を、円士郎が握った。
どきん、と心臓が音を立てるのを聞きながら、円士郎の顔を見上げると、
「あいつが、そういう冷酷なだけの男じゃねえことも知っているからだ」
円士郎はどこか悲しそうな表情で、きっぱりとそう言った。
「だからこそ──今回のことはわからねえ……!」
円士郎は怒ったように私から目を逸らして、壁で揺れている水面の光を睨みつけた。
「エン……?」
「あの野郎、いったいどういうつもりだ──!?」
実はこの縁談の裏には、伊羽青文という人の、私たちの知らない覚悟があったのだけれど……
私がそれを知るのは、全てが終わった後のことだった。
気づいたら、自然にそう漏らしてしまっていた。
「留玖……」
私のほうを向く円士郎の気配を感じながら、私は下を向いたまま、彼の袖をぎゅっとつかんだ。
以前、私は円士郎が信頼している人なら信頼できると言った。
けれど……わからなくなった。
「エンは──どうして、そんな酷いことを平然とするような冷たい人とつき合ってるの?」
震える声で尋ねた私の手を、円士郎が握った。
どきん、と心臓が音を立てるのを聞きながら、円士郎の顔を見上げると、
「あいつが、そういう冷酷なだけの男じゃねえことも知っているからだ」
円士郎はどこか悲しそうな表情で、きっぱりとそう言った。
「だからこそ──今回のことはわからねえ……!」
円士郎は怒ったように私から目を逸らして、壁で揺れている水面の光を睨みつけた。
「エン……?」
「あの野郎、いったいどういうつもりだ──!?」
実はこの縁談の裏には、伊羽青文という人の、私たちの知らない覚悟があったのだけれど……
私がそれを知るのは、全てが終わった後のことだった。