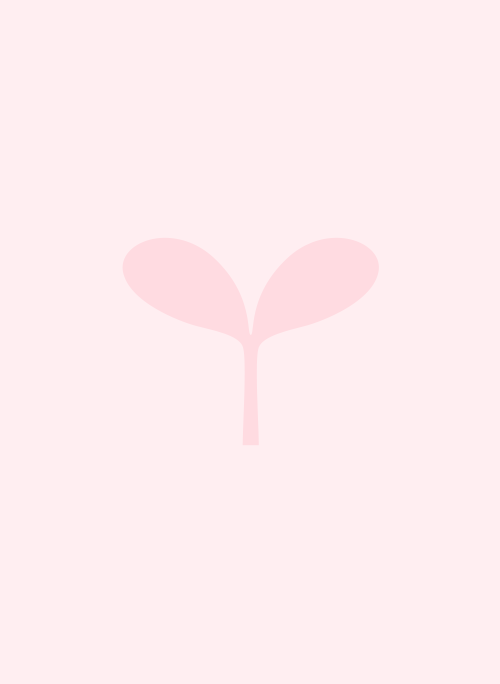戻ってくると、相変わらず屋敷の奥からは祈祷だか読経だかの声が聞こえていて、俺はげんなりした。
俺たちが百物語をした例の開かずの部屋の御祓いのために、
屋敷にはあれから連日、入れ替わり立ち替わり、偉い坊さんだの修験者だのが出入りしていて、
そんなものに効果があるなどと信じていない俺は、こいつらは単に結城家から金を巻き上げるために群がってきているようにしか思えなかった。
このままでは本気で、結城家は呪いに怯えているなどという噂が立ちかねない。
いくら母上の許しを得ている者たちとは言え、今日という今日はいい加減俺も堪忍袋の緒が限界だった。
こうなったら江戸にいる親父殿に手紙を書いて問いただしたほうがマシだ。
そう思って、俺は胡散臭い祈祷師を追い返そうと、どすどすと足音を立てて奥の部屋に向かって──
「おい! いい加減にしやがれ! 結城家は武門の家だ! 役に立たん御祓いなんざこれ以上必要ねえ……」
香でも焚いているのか、怪しげな匂いの漂ってくる部屋の襖を開け放って怒鳴り込み、
そこにいた人物を見て硬直した。
「ああ、円士郎様。こちらは城下でも高名な祈祷師の、『正慶様』です」
と、部屋に控えていた中間男が、俺も見知ったその尼僧を紹介した。
「正慶様のこの黄色い右目にはですね、何でも破魔の力が宿ってらっしゃるとのことで……」
「ただの不良品の義眼だろうが、与一ィイイ──!!」
得意げに説明する奉公人を遮って、俺はにやにや笑う尼僧の白い顔に指を突きつけて絶叫した。
俺たちが百物語をした例の開かずの部屋の御祓いのために、
屋敷にはあれから連日、入れ替わり立ち替わり、偉い坊さんだの修験者だのが出入りしていて、
そんなものに効果があるなどと信じていない俺は、こいつらは単に結城家から金を巻き上げるために群がってきているようにしか思えなかった。
このままでは本気で、結城家は呪いに怯えているなどという噂が立ちかねない。
いくら母上の許しを得ている者たちとは言え、今日という今日はいい加減俺も堪忍袋の緒が限界だった。
こうなったら江戸にいる親父殿に手紙を書いて問いただしたほうがマシだ。
そう思って、俺は胡散臭い祈祷師を追い返そうと、どすどすと足音を立てて奥の部屋に向かって──
「おい! いい加減にしやがれ! 結城家は武門の家だ! 役に立たん御祓いなんざこれ以上必要ねえ……」
香でも焚いているのか、怪しげな匂いの漂ってくる部屋の襖を開け放って怒鳴り込み、
そこにいた人物を見て硬直した。
「ああ、円士郎様。こちらは城下でも高名な祈祷師の、『正慶様』です」
と、部屋に控えていた中間男が、俺も見知ったその尼僧を紹介した。
「正慶様のこの黄色い右目にはですね、何でも破魔の力が宿ってらっしゃるとのことで……」
「ただの不良品の義眼だろうが、与一ィイイ──!!」
得意げに説明する奉公人を遮って、俺はにやにや笑う尼僧の白い顔に指を突きつけて絶叫した。