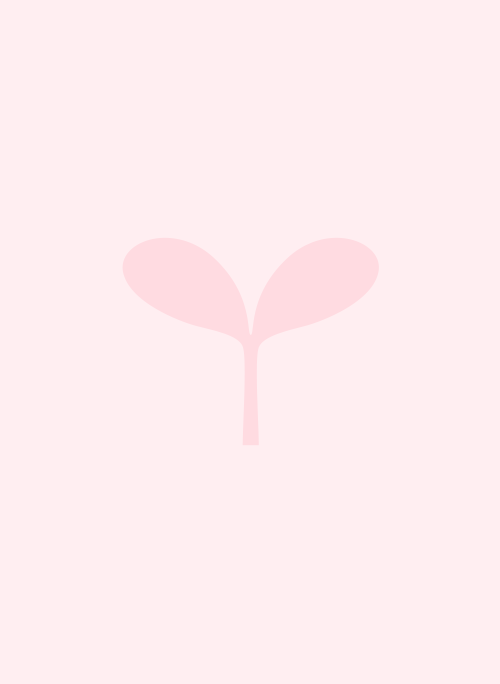しばらくの沈黙の後、王はぽつりと苦笑するように呟いた。
「もし余が彼奴を喰ろうたら、ライアは泣くのだろうな」
―リンを想って、―
月光と同じ色で輝く髪の奥、同じく月光色の双眸が細く月を見上げた。
「無論、泣くでしょうな。
…『羽憑き』の青年、リン・リカルドと、貴方様の事を想って」
ぱっとメイスフォールを振り返った王の姿は、凄艶、月の申し子を思わせる程に美しい。
不安定なその瞳は、母にすがる幼子のようだ、とメイスフォールは思う。
「ライアは、貴方様を見捨てたりなど致しませぬ」
言って含めるように、優しく。
温度を感じさせない月が、ただぽっかりと夜空に浮かんでいた。
「もし余が彼奴を喰ろうたら、ライアは泣くのだろうな」
―リンを想って、―
月光と同じ色で輝く髪の奥、同じく月光色の双眸が細く月を見上げた。
「無論、泣くでしょうな。
…『羽憑き』の青年、リン・リカルドと、貴方様の事を想って」
ぱっとメイスフォールを振り返った王の姿は、凄艶、月の申し子を思わせる程に美しい。
不安定なその瞳は、母にすがる幼子のようだ、とメイスフォールは思う。
「ライアは、貴方様を見捨てたりなど致しませぬ」
言って含めるように、優しく。
温度を感じさせない月が、ただぽっかりと夜空に浮かんでいた。