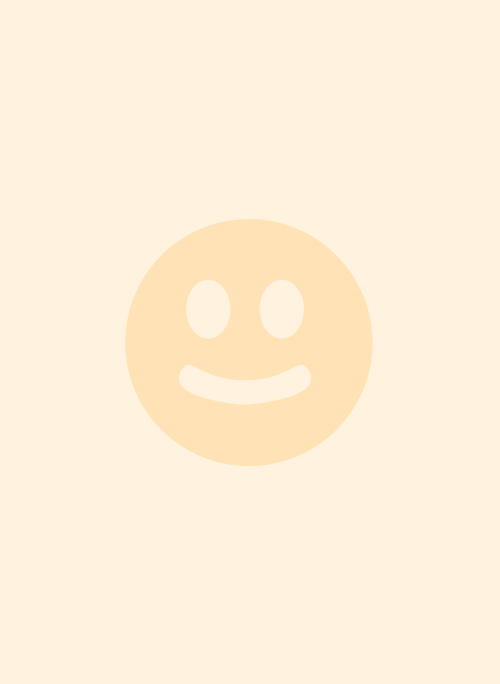「あれえ、佐和ちゃん。こんにちはー」
――え?
わたしは瞬きして彼を見た。
さっきの顔は、見間違いだった?
そう思うほど、明るく人懐っこい笑顔向けられて、怖ず怖ずと頭を下げた。
「こんにちは」
つい声が小さくなる。
時田くんは困ったように首を傾げた。
「ごめん。また怯えさせちゃった? さっきちょっと嫌なことあって……怖い顔してたかな?」
「…いえ」
違和感を感じながらも、わたしは少しほっとして、首を振った。
あの敵意に満ちた目がわたしに向けられたものだったとしたら――
――そう考えるのは、怖い。
まるで、見えないナイフを突き付けられたように。
鋭くて。
直情的な悪意だったから。
――え?
わたしは瞬きして彼を見た。
さっきの顔は、見間違いだった?
そう思うほど、明るく人懐っこい笑顔向けられて、怖ず怖ずと頭を下げた。
「こんにちは」
つい声が小さくなる。
時田くんは困ったように首を傾げた。
「ごめん。また怯えさせちゃった? さっきちょっと嫌なことあって……怖い顔してたかな?」
「…いえ」
違和感を感じながらも、わたしは少しほっとして、首を振った。
あの敵意に満ちた目がわたしに向けられたものだったとしたら――
――そう考えるのは、怖い。
まるで、見えないナイフを突き付けられたように。
鋭くて。
直情的な悪意だったから。