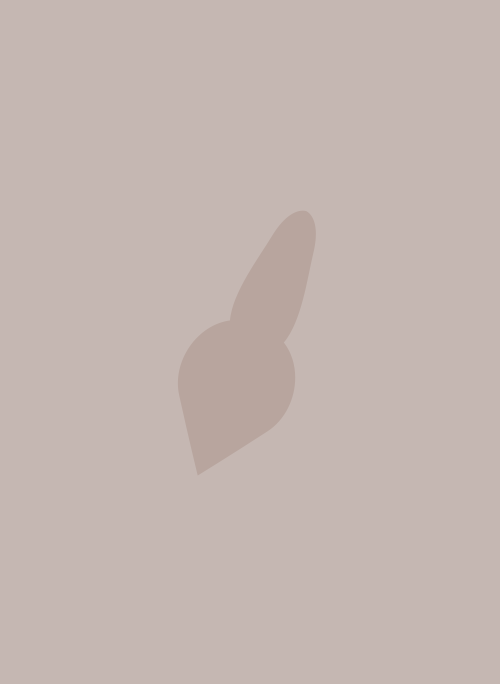「ようこそお越しくださいました?勝手に連れてきて何言っているの?冗談も大概にして」
気付いたら私は少年に対し何かが爆発したかのように捲くし上げていた。
睨みながら少年を見つめると、彼の瞳が滲んできた。
「えっ……」
そんな風な表情をされると、私が悪いみたいだ。
そのせいか怒りが一時的に落ち着き、私は怒りと言えばいいか、困惑と言えばいいか分からない表情で彼の様子をうかがった。
「すいませんでした。急いでいたもので……」
すると、少年は私にすがるように涙目で言った。
怒っていても何となく可愛く思ってしまうその容姿のせいか、毒気が抜かれてしまうような妙な感覚に陥った。
「勝手に連れてきてすみませんでした。けど“僕ら”にはあなたが必要だったんです」
必死に可愛らしく何かを伝えようとする少年。
何か彼の話を聞いていたら、自分がいけないように感じてきた。
「うん、わっわかったから。とっ、とりあえず今の状況を教えて」
その可愛さに私は負けてしまい、子供を慰めるようにやさしく言う。
私の怒りはどうやら不完全燃焼で終わってしまったらしい。
「はあ……」
行き場のない怒りがため息としてでた。