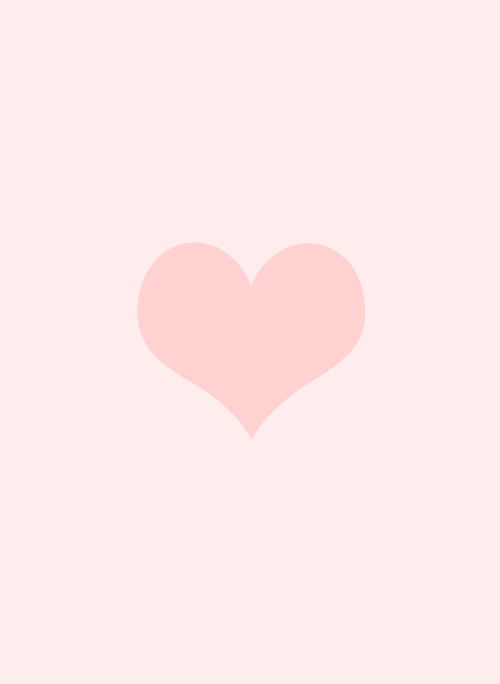「ちょっと。いつまで、そうしてるつもり?」
「そんなこと言われても……」
「もう、そのボタン押すだけじゃん?早く掛けちゃいなよっ」
あたし達は、帰り道で通る信号の前で、立ち止まっている。
ここから、お互いに家の方向が違うので、2人はいつもここでバイバイする。
でも今なぜか、あたしは雄哉くんに、電話を掛けなきゃいけなくなっちゃって。
その電話で、勉強教えてって言わなきゃいけなくなっちゃって。
「てか、今掛けても仕事中だと思うんだけど。」
「でも後で、履歴見て気づくわけだし、向こうから掛け直してくれるかも!」
きっと、あたしが電話掛けるまで、意地でも帰らないんだぁ…。
あたしは、さっきから手に持ってる携帯を、もう一度持ち直した。
そして、親指を通話ボタンの上に乗せる。
―――親指に、力を込めた。