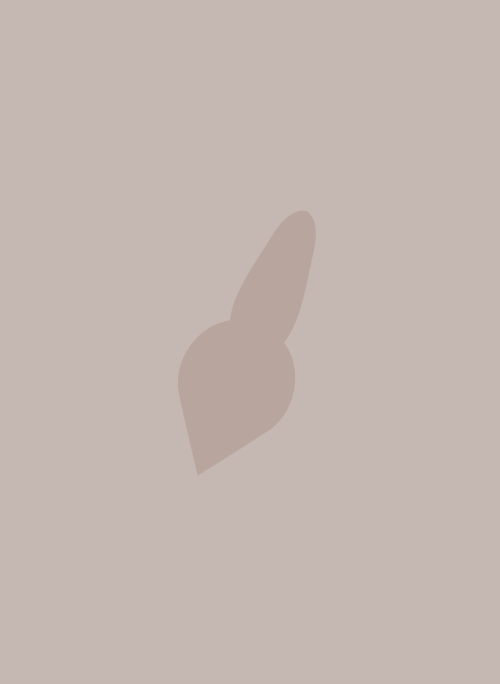どれだけ走ったのだろう。
家へと辿り着く通い慣れた筈の道程が、やたらと遠く感じた。
父と二人で暮らす小屋に辿り着いた頃には息が切れて。
早くと急く気持ちとは裏腹に、確かめるのが怖い。
半開きになった扉を、ゴクリと一度喉を鳴らしてからゆっくりと開ける。
「父、さん…?」
薄暗い室内。
灯りが消えている。
可笑しい、おかしい、オカシイ。
確かめるべきではないと、本能が告げる。
だけど、だけど!
「お、父さん」
ギィ、と蝶番を軋ませて扉を開けた、その時だった。
雲に隠れていた月が現れ、その光で小屋を照らしたのだ。
「お」
父さん。
呼び掛ける筈の言葉は声にならず。
変わりに細い悲鳴が辺りに響いた。
家へと辿り着く通い慣れた筈の道程が、やたらと遠く感じた。
父と二人で暮らす小屋に辿り着いた頃には息が切れて。
早くと急く気持ちとは裏腹に、確かめるのが怖い。
半開きになった扉を、ゴクリと一度喉を鳴らしてからゆっくりと開ける。
「父、さん…?」
薄暗い室内。
灯りが消えている。
可笑しい、おかしい、オカシイ。
確かめるべきではないと、本能が告げる。
だけど、だけど!
「お、父さん」
ギィ、と蝶番を軋ませて扉を開けた、その時だった。
雲に隠れていた月が現れ、その光で小屋を照らしたのだ。
「お」
父さん。
呼び掛ける筈の言葉は声にならず。
変わりに細い悲鳴が辺りに響いた。