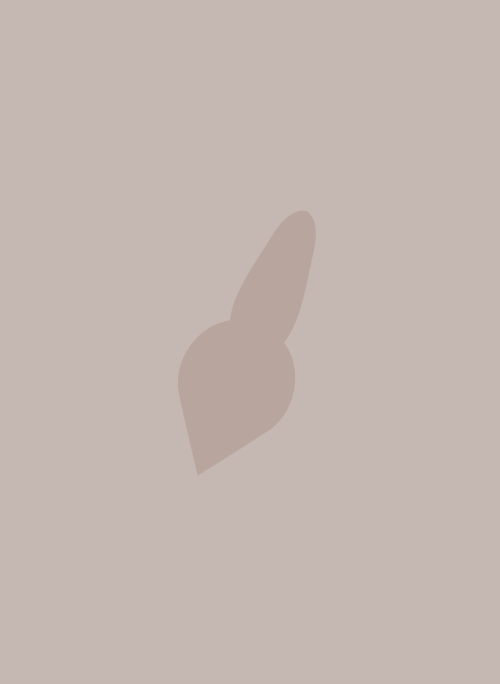その日は父に頼まれて遠い客の所まで使いに行った。
父の作品を良く買ってくれる、言わば上客だったのだけれども。
今日中に届けるように、と珍しく父が念を押すから、急ぎの品だと思ったのに。
届けに行った婦人の様子は明らかに早い仕上がりを驚いていたのだ。
違和感を感じる。
父が納期を間違えたことは一度もない。
何かが、おかしい。
自分の勘は外れたことがないのだ。
その勘が告げる。
もう直ぐで着く筈の街の様子が何だかおかしいのだと。
ドクリ、と心臓が嫌な音を立てる。
血生臭い風。
街の灯りは付いているのに、誰の気配も感じない。
何の気配も感じない。
何時もはリイエンに気さくに声を掛けてくれる、お喋り好きなおばさんすらいない。
ドクリ。
心臓がもう一度強く跳ねる。
父の元に急がねば。
行ってその無事を確かめなければ。
リイエンは見えない恐怖でもたつく足で必死に家へと走った。
父の作品を良く買ってくれる、言わば上客だったのだけれども。
今日中に届けるように、と珍しく父が念を押すから、急ぎの品だと思ったのに。
届けに行った婦人の様子は明らかに早い仕上がりを驚いていたのだ。
違和感を感じる。
父が納期を間違えたことは一度もない。
何かが、おかしい。
自分の勘は外れたことがないのだ。
その勘が告げる。
もう直ぐで着く筈の街の様子が何だかおかしいのだと。
ドクリ、と心臓が嫌な音を立てる。
血生臭い風。
街の灯りは付いているのに、誰の気配も感じない。
何の気配も感じない。
何時もはリイエンに気さくに声を掛けてくれる、お喋り好きなおばさんすらいない。
ドクリ。
心臓がもう一度強く跳ねる。
父の元に急がねば。
行ってその無事を確かめなければ。
リイエンは見えない恐怖でもたつく足で必死に家へと走った。