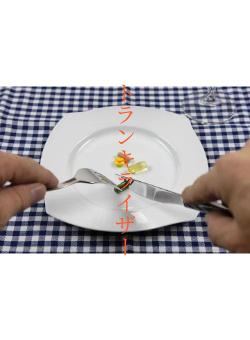「私は大丈夫。潤が私を守ってくれてたから、私は平気。潤は?大丈夫なの?」
「へ、いき。いた、けど」
だいぶ声が出るようになってきた。恭華と俺の周りにはたくさんの人が、囲むように立っていた。辺りは騒がしい。
「馬鹿、痛くて平気なはずがないでしょっ?なんで突っ込んできたのよ。下手したら、潤が、・・・潤がぁ」
言いかけた途中でボロボロと涙を流して、恭華は見たこともないくらい、泣き崩れた。痛む俺の体の上で泣く恭華。
痛みがある。俺は生きてるんだ。ゆっくりと、手を伸ばし、恭華の髪に触れた。触れれるんだ。これは夢でも、幻覚でもない。これは俺が求めていた、現在だ。
「ははっ」
「何?大丈夫?」
急に笑った俺に驚いて、恭華は顔を上げた。