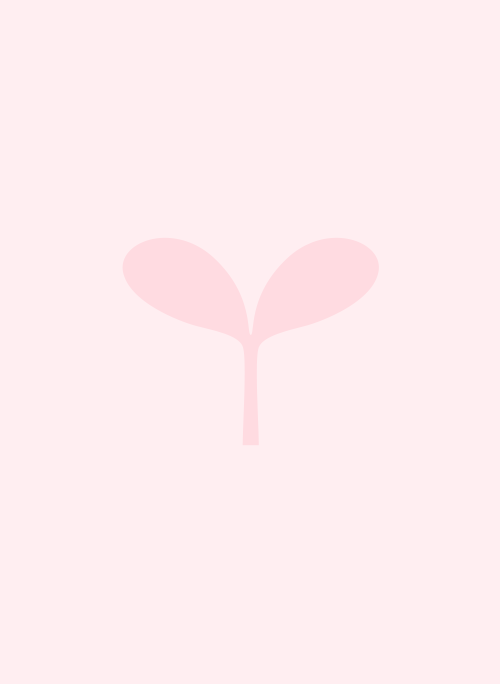被せるように遮った俺の声はさっきまでと同じ程の調子なのに自分でも少しびっくりするほど強くなった。
芹緒も驚いたのか口をつぐむ。
「今はお前からしちゃ全然使いモンになんねぇくらい弱ぇがよ、お前の相棒になったからには一緒に背負えるくらいにゃ並んでいてぇからよ」
始まりは唐突で、強引なものではあった。
それでも踏み込むと決めたのは俺だ。
そして芹緒は仕事の相方として俺を選び、その俺の為に一つ仕事を増やしている。
戌神を還した夜に決めたのだ。
芹緒を護る、って。
まぁ、つい最近色々と教えられ始めた俺なんかが急に出来るはずもなくこうして護られる一方を受け入れなきゃならねえ現状を黙認してんのは何とも情けない話ではあるのだが。
少し、間があった。
黙ったままの芹緒を怪訝に思った辺りで、俺は予想以上に周囲の明度が上がってきている事に気付いた。
お袋は黙認してくれているが親父はあの変人をあまり、というか大分良く思っていない。
親父が起きる前に帰らなきゃならない。
俺が朝帰りをする理由が一つしかないからごまかしが効かないのだ。
「やべ、親父が起きる前に帰らねぇとどやされんだ。おい芹緒、朝飯食ったか」
「へっ?まだですが…」
「うちで食ってけ。俺がお前の近くにいる分にゃ何の問題もねぇだろ」
「ぅええっ!?いっ良い訳ないじゃないですか!こんな朝早くから他所様のお家にお邪魔するなんて!!」
さすが旧家育ち(予想)。
「うちはそんなん気にする家じゃねぇんだよ。理人なんて俺がいなくても勝手に来て泊り前提で居座ったりしてんだぞ」
ほっといたら平気で食事を抜きそうだと思ったら眼の前で食わせる方が安心だと思い至ったってのが実のとこの理由だ。
芹緒も驚いたのか口をつぐむ。
「今はお前からしちゃ全然使いモンになんねぇくらい弱ぇがよ、お前の相棒になったからには一緒に背負えるくらいにゃ並んでいてぇからよ」
始まりは唐突で、強引なものではあった。
それでも踏み込むと決めたのは俺だ。
そして芹緒は仕事の相方として俺を選び、その俺の為に一つ仕事を増やしている。
戌神を還した夜に決めたのだ。
芹緒を護る、って。
まぁ、つい最近色々と教えられ始めた俺なんかが急に出来るはずもなくこうして護られる一方を受け入れなきゃならねえ現状を黙認してんのは何とも情けない話ではあるのだが。
少し、間があった。
黙ったままの芹緒を怪訝に思った辺りで、俺は予想以上に周囲の明度が上がってきている事に気付いた。
お袋は黙認してくれているが親父はあの変人をあまり、というか大分良く思っていない。
親父が起きる前に帰らなきゃならない。
俺が朝帰りをする理由が一つしかないからごまかしが効かないのだ。
「やべ、親父が起きる前に帰らねぇとどやされんだ。おい芹緒、朝飯食ったか」
「へっ?まだですが…」
「うちで食ってけ。俺がお前の近くにいる分にゃ何の問題もねぇだろ」
「ぅええっ!?いっ良い訳ないじゃないですか!こんな朝早くから他所様のお家にお邪魔するなんて!!」
さすが旧家育ち(予想)。
「うちはそんなん気にする家じゃねぇんだよ。理人なんて俺がいなくても勝手に来て泊り前提で居座ったりしてんだぞ」
ほっといたら平気で食事を抜きそうだと思ったら眼の前で食わせる方が安心だと思い至ったってのが実のとこの理由だ。