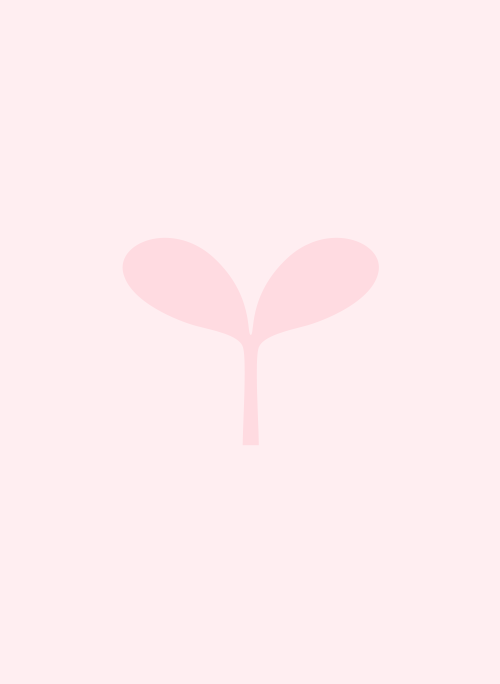裂けた空間から現れる、蒼い刀身、朱い柄、そして、色彩の定まらない玉。
細身の剣はかしづくように芹緒の手元に収まった。
「ちょうどいいや」
「それで」
「あいつを」
「刺してよ」
突然場を揺るがせた声にそっちを向くと、学ランを着た二人の兄弟が、立ち上がりこちらを見ていた。
どこかで見た事が…
芹緒が静かに口を開く。
「パン屋さんの所でお見かけしましたね…」
そうだ。
パンの耳を貰っていた…ここの家の人間だったのか。
兄弟の額には一対ずつ、後ろから視認した鬼の角が生えていた。
そしてその角にはおどろおどろしい火が灯っている。
気持ちが悪くなるような青白い火だった。
「あいつが」
「あいつが悪い」
「僕達の事なんて」
「まるで見てなかった」
早口で交互に繰り出される言葉に、胃がむかむかしてくる。
「いつも」
「いつも」
「いつも」
「いつも!」
「収入源もないのに」
「家にはいない」
「何処に行ってるのかも」
「何をしてるのかも」
「なにも」「なにも僕」「達には言」「わないま」「まお金も」「入れずへ」「らへらへ」「らへら…」
…胸糞悪い。
吐き気がした。
「その申し出は受けかねますね。仏になった故人をなおもって傷付けるのは、僕の理念に反します」
芹緒が、凛と声を響かせて俺の前に立つ。
「そもそも、この剣は人を斬る為の物ではない」
恨みがましい眼をぎょろつかせて爬虫類のような四つの目玉が俺達二人を睨む。
鼻筋が浮き上がり外側に向かうように変容した目は、牛にも馬にも、人にも見えた。
細身の剣はかしづくように芹緒の手元に収まった。
「ちょうどいいや」
「それで」
「あいつを」
「刺してよ」
突然場を揺るがせた声にそっちを向くと、学ランを着た二人の兄弟が、立ち上がりこちらを見ていた。
どこかで見た事が…
芹緒が静かに口を開く。
「パン屋さんの所でお見かけしましたね…」
そうだ。
パンの耳を貰っていた…ここの家の人間だったのか。
兄弟の額には一対ずつ、後ろから視認した鬼の角が生えていた。
そしてその角にはおどろおどろしい火が灯っている。
気持ちが悪くなるような青白い火だった。
「あいつが」
「あいつが悪い」
「僕達の事なんて」
「まるで見てなかった」
早口で交互に繰り出される言葉に、胃がむかむかしてくる。
「いつも」
「いつも」
「いつも」
「いつも!」
「収入源もないのに」
「家にはいない」
「何処に行ってるのかも」
「何をしてるのかも」
「なにも」「なにも僕」「達には言」「わないま」「まお金も」「入れずへ」「らへらへ」「らへら…」
…胸糞悪い。
吐き気がした。
「その申し出は受けかねますね。仏になった故人をなおもって傷付けるのは、僕の理念に反します」
芹緒が、凛と声を響かせて俺の前に立つ。
「そもそも、この剣は人を斬る為の物ではない」
恨みがましい眼をぎょろつかせて爬虫類のような四つの目玉が俺達二人を睨む。
鼻筋が浮き上がり外側に向かうように変容した目は、牛にも馬にも、人にも見えた。