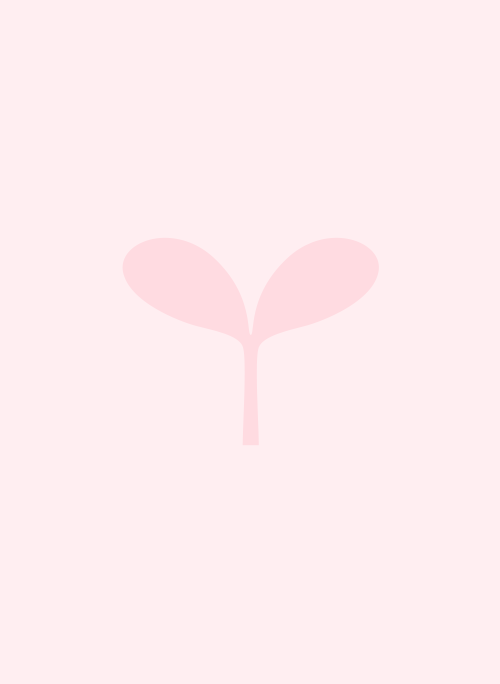「ホームに付いてたカメラにも影像が残っていてなぁ、
自殺の方向で固まりそうだよ」
いつも俺が連れて行かれる警察署のすぐ横の喫茶店を通り過ぎて、小さな路地を曲がった所にある小さな喫茶店。
恐ろしく顔の整った若いマスターと、太めの眉毛が凛々しいオカッパの女子高生バイト、そしてカウンターにいるどうしても西洋人形にしか見えない紅い眼をした少女の他には客の姿が見当たらない。
こんな所があるなんて知らなかったが、確かにここなら話を圦さんの同僚に聞かれる心配もないのだろう。
バイトが水とおしぼりを持って来た所に珈琲を三つ頼むと、圦さんはぼそりとそう呟いた。
そして、続ける。
「子供も残しちまって……相当マイっちまってたのかね…」
「子供がいたんスか?」
俺の問いに圦サンは取り出した煙草に火を点ける為、口元に手をかざしながら視線だけで頷いた。
「しかも二人だ。
まだまだ思春期真っ只中だろうってのに」
ゆらゆらと立ちのぼる煙草の煙が、窓から入る西日をくぐって、天井で回るファンに掻き消されていく。