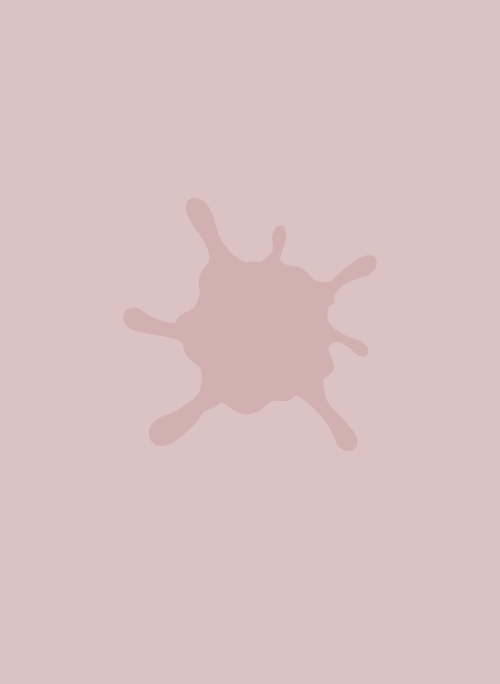「……ってぇ…」
傷だらけで、足は疲労が溜まって重たかった。身体中が疲労の鎖で縛り付けられたように。
胸は痛いし頭も痛い。目蓋も重たく、非道く眠たい。
脳は既に思考回路が潰れ気味で、現実と幻想の狭間が認識できなくなってくる。
これは全て悪い夢で、目が覚めればいつものように疲れてベッドで眠っていて、もうすぐ誰かが…多分、レイヴン辺りが嫌味な起こし方で、目を覚まさせてくれるような、そんな淡い期待を抱くほどに。
「クロウ、行こう」
クロウのそんな現実逃避を引き戻すのは、ルックの声だ。
全ては現実。
命を狙われていることも。
仲間が二人、死んだことも。
「ルック…悪い、レイヴン……守れなかった」
言う、クロウの腕を、今度はルックが掴んで走り出す。
二人の友人の死を目の当たりにして、流石のクロウも目に見えて疲弊していた。
ルックは何も言わない。
ただ、生き延びなければいけないと言う、そんな使命感だけがルックの足を、思考を、動かしていた。
全員が居なければ、意味がなかった。
だけど、そんな綺麗事は通用しなくて、失くしていくものなんて塞ぎきれないほどに溢れていて、小さな自分の手のひらには沢山のものがあったということを今更ながらに知る。
まるで砂のように、サラサラとこぼれる大切だったものたち。
いや、今でも大切なものたちだ。