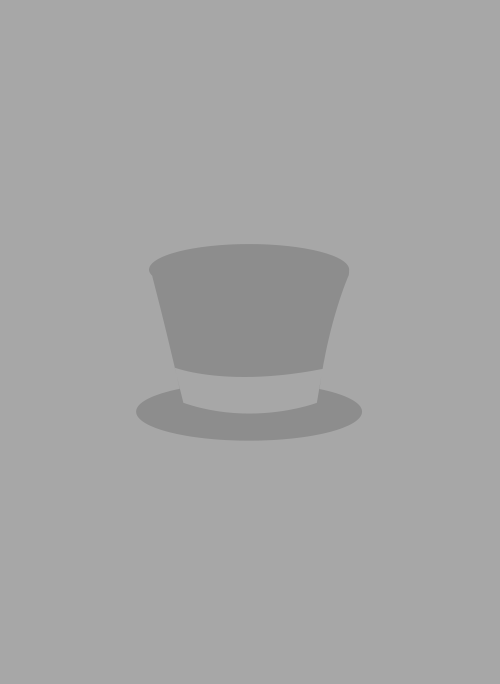一羽の鷲が悠々と高い空を舞うのを見上げて、男はやれやれと苦笑した。
飼っているわけでもないのに、なぜかずいぶん長い間自分と行動をともにしている。
実際は、見張られているのかもしれないが。
男は村の中に唯一ある水源で、桶いっぱいに水を汲んだ。
じりじりと焼け付く太陽が肌を刺す。
男は家まで帰ることを早々にあきらめ、いったん木陰で休憩することにした。
額には、玉のような汗。
手ぬぐいを湿らせて顔を拭こうと、肩にかけた袋を床において、男は中に手を入れた。
感触で布を掴み、引っ張り出す。
と、不意に男の動きが止まった。
・・これは、あの時の。
それは刀傷を負ったときに、少女が自分の衣を裂いて手当てしてくれた布だった。
血がどす黒く変色し、ぼろぼろになっているので、元が美しい藍色の衣だったとは想像もできない。
・・まったく、未練だな。