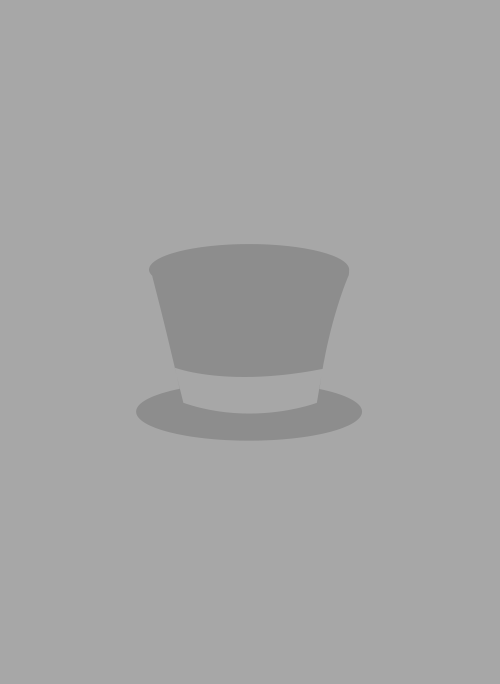「お前、僕の昼寝の邪魔をするのか」
完全な言いがかりだとわかっていても、つい意地悪をしてしまう。
案の定、そんなわけでは、などとレリーの戸惑った声が届き、ソードは満足げな笑みを浮かべた。
「お願いです。降りてきてください」
再びレリーが泣きそうな声を上げたところで、ソードは両足を枝にまたがるようにおろして下を見下ろした。
両手は枝について、姿勢よく馬に乗っているような格好だ。
「お前がここまで僕を連れにきたら考えてやるよ」
猫のような瞳で、口の端を持ち上げるソード。
「そんな!無理です」
「いいから来い。命令だ。手をひっぱってやるから。そこのうろに足をかけるんだ」
ソードの視線の先には、確かに小さな穴がある。
そこに足を入れて手を伸ばせば、ソードの足に触れられそうではあるが。
レリーは目の前にあるごつごつした幹を、舐めるようにして見上げた。
枝と葉の間から、握りこぶしほどの大きさのソードの顔が見える。
木登りの経験のないレリーには、それがどれくらい大変なことかの想像もつかない。
絶対に無理だ、そう思ったとき、穏やかな声とともに長い腕が自分に向かって伸びてきた。
「大丈夫だ、ほら」