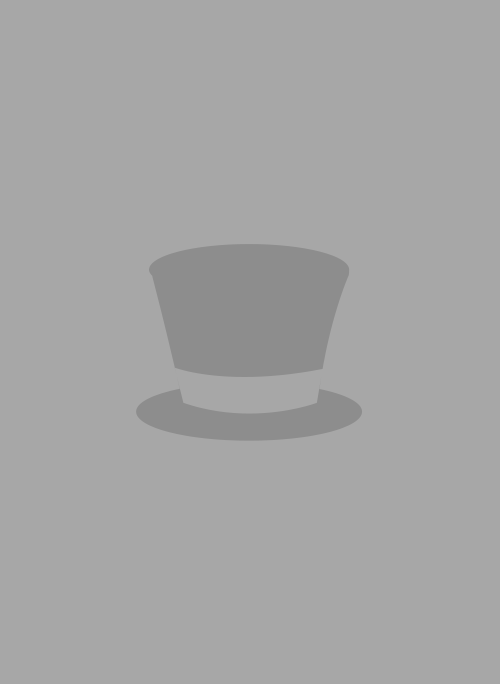大木の下で、少女は大きな瞳にいっぱいの涙をたたえていた。
本当は、部屋に戻って大声で泣きたい。
けれど、自分が与えられている部屋は、一人部屋ではなく、
そこに私的な空間など存在しない。
一人になりたいとき、彼女はよくこうして、木の下に身を寄せていた。
風雨から身を守ってくれる大木は、彼女にとって親の腕に抱かれているように落ち着きを感じる場所だった。
母が死んだ頃は、毎日ここで泣いていた。
そのうち、ここは、毎日の出来事を報告する場所になった。
何を話しかけても、木が答えることはない。
しかし、それが彼女にはかえって心地よかった。
下手に本音を漏らせない魔物のようなこの棲家では、少しの油断が破滅を意味する。
王位継承を巡り、水面下での争いが繰り広げられる王宮では、
言葉が凶器になりえる。
どの王子が王に相応しいなどと漏らせば、敵対している側からどんな仕打ちを受けるかもしれない。
侍女である自分でさえ、こんなにも神経をする減らしているのだから、
その当事者の心労は、計り知れないものがあるだろう。
少女が、ため息をこぼしたとき、
「レリー」
と、自分を呼ぶ声が聞こえて、レリーの体がびくりとはねた。