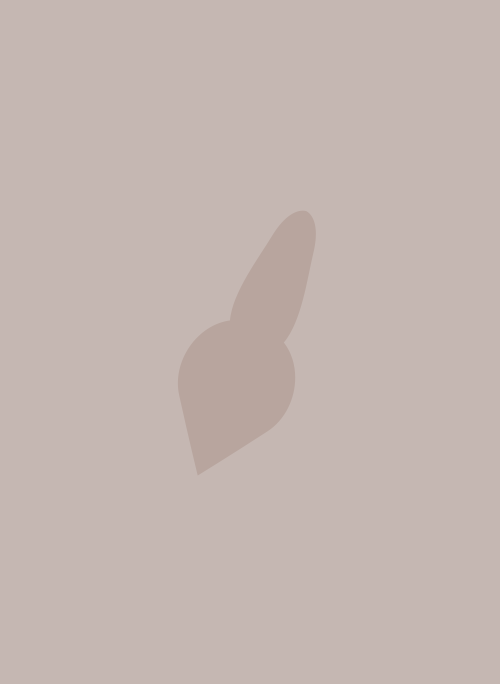涼村さんは、毎日遅くまで
残業していた。
製造部署では、定時になっ
たら、競うように帰って行
く女子社員ばかりを見てい
た俺には新鮮だった。
ある日、事務所には、俺と
涼村さんだけが残って、パ
ソコン画面と睨めっこして
いた。
午後8時を過ぎた頃、涼村
さんが、
「私、26歳ぐらいに見ら
れるんです。話し方とか態
度が偉そうだから」と言っ
た。
「だろうね」と返したら、
「ヒドイ!私だってまだ、
21歳の女の子ですよ」
「だね。遊びたい盛りなの
に、よくやってるよ」
「ありがとう。私、夏生さ
んに感謝していることがあ
るんです」
「え?」と、驚いた顔をす
る俺に、涼村さんは、デス
クの引出しから、一枚のメ
モを出して渡した。
そのメモには、
『工務の仕事をしてくださ
い』と、一言だけ書かれて
いた。
彼女宛に、俺の署名で。
「新入社員の頃、まだ何も
分らずに、製造指示の書類
を、夏生さんのデスクに置
いておいたら、そのメモを
付けて叩き返されました。
よく調べると、部品も揃っ
ていない状態で、製品が造
れるハズもなかったんです
…」
「忘れてたな」と言って、
俺はメモを涼村さんに返し
た。
「最初は、何なの?と思っ
たんですけど、新人の私も
ちゃんと社員として見てく
れてるんだと思ってうれし
くなったんです。これが、
私の原点なんです」
「そっか。俺もここで、が
んばらなきゃな。涼村さん
みたいに」
「はい」
「じゃあ、ちょっと一服し
ようか?コーヒーでも奢る
から」
「はい。でも私は、オレン
ジジュースがイイです」と
言って、負けず嫌いの涼村
さんは、いつものように薄
く笑った。
残業していた。
製造部署では、定時になっ
たら、競うように帰って行
く女子社員ばかりを見てい
た俺には新鮮だった。
ある日、事務所には、俺と
涼村さんだけが残って、パ
ソコン画面と睨めっこして
いた。
午後8時を過ぎた頃、涼村
さんが、
「私、26歳ぐらいに見ら
れるんです。話し方とか態
度が偉そうだから」と言っ
た。
「だろうね」と返したら、
「ヒドイ!私だってまだ、
21歳の女の子ですよ」
「だね。遊びたい盛りなの
に、よくやってるよ」
「ありがとう。私、夏生さ
んに感謝していることがあ
るんです」
「え?」と、驚いた顔をす
る俺に、涼村さんは、デス
クの引出しから、一枚のメ
モを出して渡した。
そのメモには、
『工務の仕事をしてくださ
い』と、一言だけ書かれて
いた。
彼女宛に、俺の署名で。
「新入社員の頃、まだ何も
分らずに、製造指示の書類
を、夏生さんのデスクに置
いておいたら、そのメモを
付けて叩き返されました。
よく調べると、部品も揃っ
ていない状態で、製品が造
れるハズもなかったんです
…」
「忘れてたな」と言って、
俺はメモを涼村さんに返し
た。
「最初は、何なの?と思っ
たんですけど、新人の私も
ちゃんと社員として見てく
れてるんだと思ってうれし
くなったんです。これが、
私の原点なんです」
「そっか。俺もここで、が
んばらなきゃな。涼村さん
みたいに」
「はい」
「じゃあ、ちょっと一服し
ようか?コーヒーでも奢る
から」
「はい。でも私は、オレン
ジジュースがイイです」と
言って、負けず嫌いの涼村
さんは、いつものように薄
く笑った。