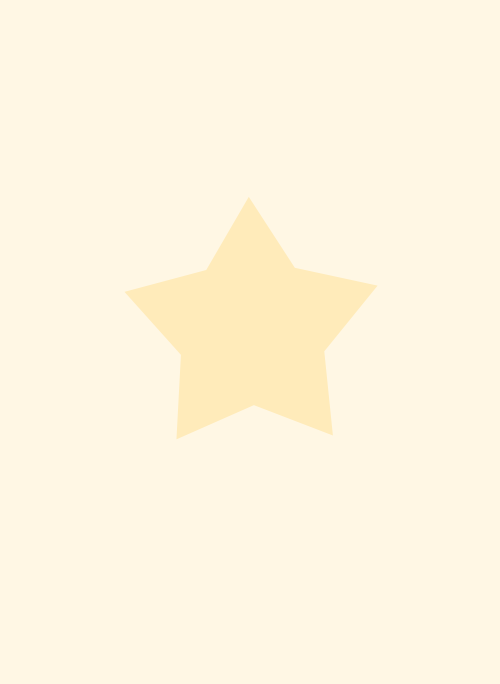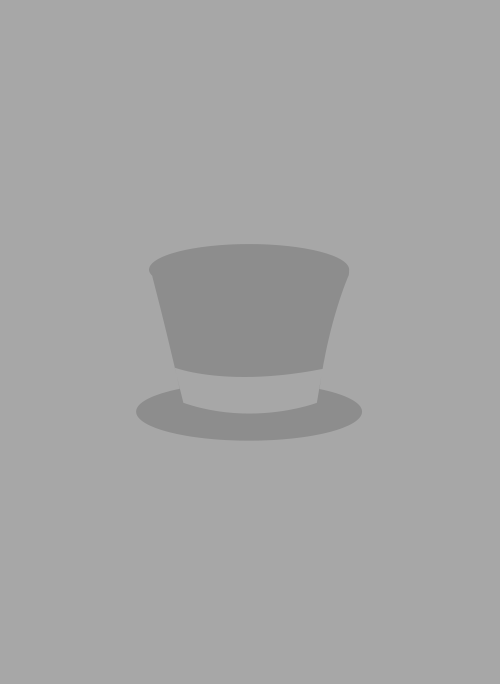「父さん達だって、常識のある人間だ。その少女が殺人を犯したのなら、その罪は償うべきだと思った。たとえ14歳未満で罪を問われなかったとしても、自分のやった事をはっきりと自覚して一生その罪を償っていかなければならないと思った。だけど、不思議に思ったんだ…身長130センチ程の小柄な少女が果たして散弾銃を打つことが出来るのかって」
「私…じゃないの?」
初めて碧が向きを変えて肇の方を見た。
「顔の手術をしながら俺は、少女の手から硝煙反応を調べた。もちろん着ていた白いセーターも調べた」
「硝煙反応は出なかった?」
「ああ。出なかった。しかも少女の白いセーターを真っ赤に染めていた血痕はその子の物ではなかったんだ…違う血液型、つまり川村健吾と美津子夫妻の物だったんだ。知っての通り散弾銃は銃身が長い。それで打ったとしたらあれほどの返り血を浴びるだろうか?…そこで俺は一つの結論に達した。少女の両親が何者かによって銃殺され、少女は至近距離に居たため返り血を浴び、なおかつ自分も負傷したのではないかと」
「…ただの推測よ。私が殺したのよ。それでいいじゃない。私が発見されたのは4月だからもう時効だわ…もっとも10歳だったんだから罪にはならないか」
自嘲気味に唇をゆがめる碧の頬を和哉が思いっきり張った。驚くほどの大きな音を立てて碧がのけぞる。
「馬鹿!…どうして自分を信じられないんだ。俺はお前を信じるぞ。碧は誰も殺しちゃいない、誰も傷つけちゃいないんだよ」
「碧、これを見てくれ」
「私…じゃないの?」
初めて碧が向きを変えて肇の方を見た。
「顔の手術をしながら俺は、少女の手から硝煙反応を調べた。もちろん着ていた白いセーターも調べた」
「硝煙反応は出なかった?」
「ああ。出なかった。しかも少女の白いセーターを真っ赤に染めていた血痕はその子の物ではなかったんだ…違う血液型、つまり川村健吾と美津子夫妻の物だったんだ。知っての通り散弾銃は銃身が長い。それで打ったとしたらあれほどの返り血を浴びるだろうか?…そこで俺は一つの結論に達した。少女の両親が何者かによって銃殺され、少女は至近距離に居たため返り血を浴び、なおかつ自分も負傷したのではないかと」
「…ただの推測よ。私が殺したのよ。それでいいじゃない。私が発見されたのは4月だからもう時効だわ…もっとも10歳だったんだから罪にはならないか」
自嘲気味に唇をゆがめる碧の頬を和哉が思いっきり張った。驚くほどの大きな音を立てて碧がのけぞる。
「馬鹿!…どうして自分を信じられないんだ。俺はお前を信じるぞ。碧は誰も殺しちゃいない、誰も傷つけちゃいないんだよ」
「碧、これを見てくれ」