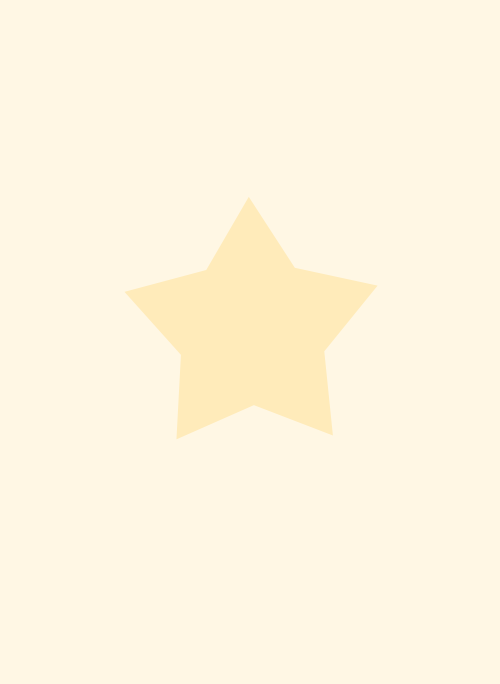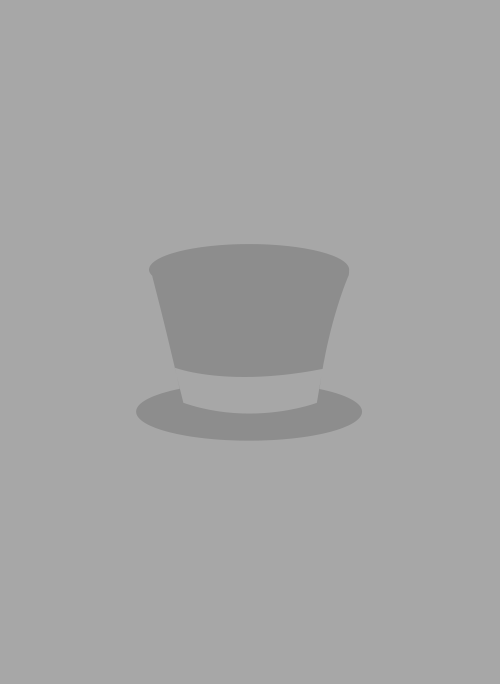降りしきる中、大きく見開かれた両目は食い入るように前方の何かを見つめ、濡れた髪が額にかかる、その表情は何かしらぞっとするような美しさ…。
(今のは碧か…?それとも…川村沙耶!)
そう思った瞬間和哉は躊躇せず後を追った。
豪雨で前が見えずらいほどだが、今碧を引き止めなければ、もう二度と沖田碧には会えないような気がして、和哉は死に物狂いで走った。
残された二人は突然の二人の行動にあっけにとられながらも後を追う。
まるで舌なめずりする大蛇のように空に描かれる光の筋に、その都度身をすくめながら3人は碧に追いついた。
目をつぶって足首まで水に入った碧は心の中で夢と同じように数を数えた。
(こうすれば怖いものなんて何時も居なくなっちゃう…大丈夫、怖くない)
初夏だというのに痺れるような水の冷たさを感じながら碧はゆっくりと目を開けた。
碧は幻覚を見ていた。
そこには10歳の碧が…いや川村沙耶が立っていた。水面を通して碧と対峙する10歳の川村沙耶。
真っ赤な服を着て手には何かを持っている。
(これはなに…私なの?…何を持っているの?)
水に浸かった足首とは逆に体は燃えるように熱い。もう自分ではどうしようもないほど手は震え、それは全身にまで広がった。
(ああ…赤い服じゃないのね。白い服…血で染まっている…誰の血?私の?)
萎えそうな心を奮い立たせてもう一度目を凝らした碧が見たのは猟銃を抱え全身血まみれで、その表情さえ分かりかねるほどの血しぶきを浴びた15年前の自分だった。
その真っ赤な海の中で見開かれた瞳は哀しげに輝き、口からは何か言葉を吐き出そうとするが出てくるのはうめき声だけ。
(今のは碧か…?それとも…川村沙耶!)
そう思った瞬間和哉は躊躇せず後を追った。
豪雨で前が見えずらいほどだが、今碧を引き止めなければ、もう二度と沖田碧には会えないような気がして、和哉は死に物狂いで走った。
残された二人は突然の二人の行動にあっけにとられながらも後を追う。
まるで舌なめずりする大蛇のように空に描かれる光の筋に、その都度身をすくめながら3人は碧に追いついた。
目をつぶって足首まで水に入った碧は心の中で夢と同じように数を数えた。
(こうすれば怖いものなんて何時も居なくなっちゃう…大丈夫、怖くない)
初夏だというのに痺れるような水の冷たさを感じながら碧はゆっくりと目を開けた。
碧は幻覚を見ていた。
そこには10歳の碧が…いや川村沙耶が立っていた。水面を通して碧と対峙する10歳の川村沙耶。
真っ赤な服を着て手には何かを持っている。
(これはなに…私なの?…何を持っているの?)
水に浸かった足首とは逆に体は燃えるように熱い。もう自分ではどうしようもないほど手は震え、それは全身にまで広がった。
(ああ…赤い服じゃないのね。白い服…血で染まっている…誰の血?私の?)
萎えそうな心を奮い立たせてもう一度目を凝らした碧が見たのは猟銃を抱え全身血まみれで、その表情さえ分かりかねるほどの血しぶきを浴びた15年前の自分だった。
その真っ赤な海の中で見開かれた瞳は哀しげに輝き、口からは何か言葉を吐き出そうとするが出てくるのはうめき声だけ。