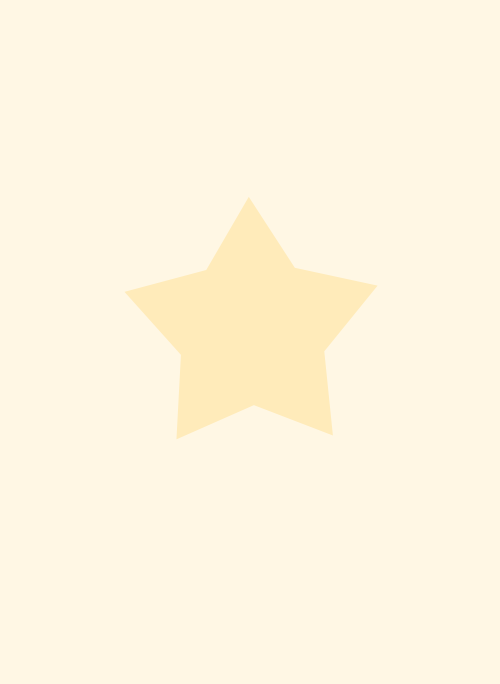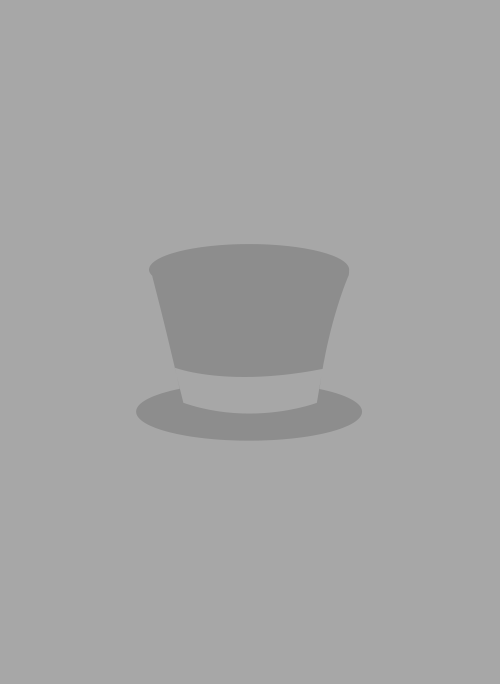「わかった・・・じゃあお茶でも飲んで行かない?私がおごるから」
「本当にいいの?ガソリンまだあるからもう少しならいけるけど・・・でもこれ以上行っても山の中ばっかりだもんね」
そういいながら静香も心なしか少しほっとした様子である。やはり相当疲れていたのだろう。
蹴飛ばすと崩れ落ちそうな扉を開けて店に入った二人は窓際の席に腰を下ろした。
机も椅子もかなりの年代を感じさせ、おそらく碧達が生まれる前から存在していそうな気配がある。
程なくして店の奥から一転の曇りも無い豊かな銀髪を整えた初老の婦人が水とお絞りを持ってきた。
「ごめんなさいね、待たしちゃって。お客さんなんて殆ど来ないから油断しちゃった」
「いえ、こちらこそ急におじゃましてすいません」
喫茶店に急にお邪魔してというのも変かなと思いながら碧は夫人の手から水を受け取った。
「コーヒー二つお願いします」
上品に微笑んだ婦人はカウンターの裏に回りサイフォンに火をかけた。
「ごめんね静香、突き合わせちゃって。疲れたでしょ」
「疲れたわよ、普段運転なんてあんまりしないから、もう足なんてパンパン。って嘘よ、全然平気。それより何にも思い出さない?頭は痛くならない?」
「うん大丈夫・・・でもやっぱり何にも思い出さないの。もう15年間も忘れたままだもん。無理かな」
「・・・かもね。でもいいじゃん、無理に思い出さなくても。きっと碧は生まれたときから10歳だったのよ」
「本当にいいの?ガソリンまだあるからもう少しならいけるけど・・・でもこれ以上行っても山の中ばっかりだもんね」
そういいながら静香も心なしか少しほっとした様子である。やはり相当疲れていたのだろう。
蹴飛ばすと崩れ落ちそうな扉を開けて店に入った二人は窓際の席に腰を下ろした。
机も椅子もかなりの年代を感じさせ、おそらく碧達が生まれる前から存在していそうな気配がある。
程なくして店の奥から一転の曇りも無い豊かな銀髪を整えた初老の婦人が水とお絞りを持ってきた。
「ごめんなさいね、待たしちゃって。お客さんなんて殆ど来ないから油断しちゃった」
「いえ、こちらこそ急におじゃましてすいません」
喫茶店に急にお邪魔してというのも変かなと思いながら碧は夫人の手から水を受け取った。
「コーヒー二つお願いします」
上品に微笑んだ婦人はカウンターの裏に回りサイフォンに火をかけた。
「ごめんね静香、突き合わせちゃって。疲れたでしょ」
「疲れたわよ、普段運転なんてあんまりしないから、もう足なんてパンパン。って嘘よ、全然平気。それより何にも思い出さない?頭は痛くならない?」
「うん大丈夫・・・でもやっぱり何にも思い出さないの。もう15年間も忘れたままだもん。無理かな」
「・・・かもね。でもいいじゃん、無理に思い出さなくても。きっと碧は生まれたときから10歳だったのよ」