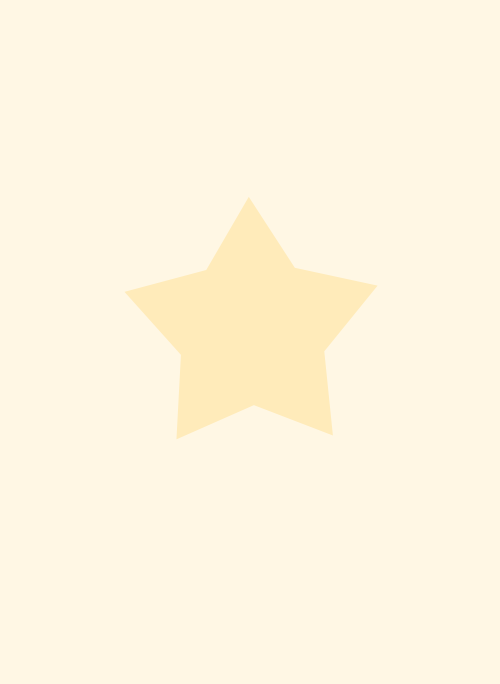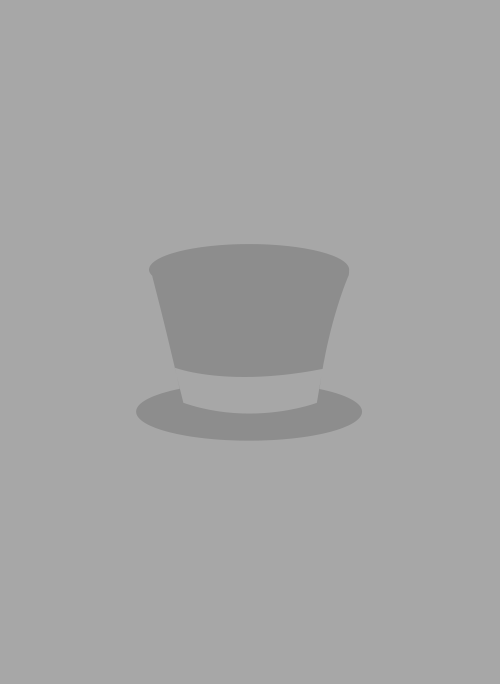『おはよう!』
碧の声に新聞を読んでいた父の沖田肇(おきた はじめ)が新聞の上から顔を出しニッコリと微笑んだ。
『おはよう碧…夏美、碧にもコーヒーを入れてやりなさい』
『いいわよコーヒーぐらい自分で出来るから、お母さんは座っていて』
腰を浮かせた母の夏美(なつみ)を手で制して碧は湯気の立つポットから熱いコーヒーをカップに注いだ。
カップの中で波打つ褐色の液体が僅かに残っていた睡魔を奪い去り、代わりに食欲と活力を与えてくれる。
父の沖田肇は今年でちょうど60才になる外科医で中規模の個人病院を開いている。
元々は大阪の大学病院でメスを握っていたのだが、看護師をしていた母の夏美と結婚し長男の和哉が5才になったのを機に生まれ故郷の和歌山県に移り住んだ。
前に聞いた話では和哉が喘息を患いその治療の為に綺麗な空気を求めたそうだが、温暖な南紀の気候が良かったのか碧の知る限り和哉にその兆候は見られない。
ロマンスグレーの豊かな銀髪を綺麗にオールバックにまとめた穏やかな風貌は血生臭い外科医よりも、むしろ芸術家を思い起こさせる。
何処までも紳士的で優しい肇は碧にとっても自慢の父である。
碧の声に新聞を読んでいた父の沖田肇(おきた はじめ)が新聞の上から顔を出しニッコリと微笑んだ。
『おはよう碧…夏美、碧にもコーヒーを入れてやりなさい』
『いいわよコーヒーぐらい自分で出来るから、お母さんは座っていて』
腰を浮かせた母の夏美(なつみ)を手で制して碧は湯気の立つポットから熱いコーヒーをカップに注いだ。
カップの中で波打つ褐色の液体が僅かに残っていた睡魔を奪い去り、代わりに食欲と活力を与えてくれる。
父の沖田肇は今年でちょうど60才になる外科医で中規模の個人病院を開いている。
元々は大阪の大学病院でメスを握っていたのだが、看護師をしていた母の夏美と結婚し長男の和哉が5才になったのを機に生まれ故郷の和歌山県に移り住んだ。
前に聞いた話では和哉が喘息を患いその治療の為に綺麗な空気を求めたそうだが、温暖な南紀の気候が良かったのか碧の知る限り和哉にその兆候は見られない。
ロマンスグレーの豊かな銀髪を綺麗にオールバックにまとめた穏やかな風貌は血生臭い外科医よりも、むしろ芸術家を思い起こさせる。
何処までも紳士的で優しい肇は碧にとっても自慢の父である。