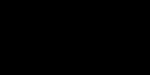明るく振る舞っていた。
だから、みんなの居ない所で声を押し殺して泣いていたんだ。
授業中だってそうだった
教科書で顔を隠しては、下を向いて泣いた。
それは自分自身が一番よく分かってた。
イケないことなんだって
……分かってたつもりだった。
けど一人で抱え込んで、その気持ちを誰にも話す訳でもなくて、胸の中にそっとしまい込んできた
それがイケなかったんだ
それが逆に……流二を苦しめていたなんて、全然分からなかった。
もし誰かに相談していたら……ちょっとは変わっていたのかな?
全てを打ち明けていたら……こんなに辛い思いをしなくて済んだのかな?
今更だけど、そんな考えが頭をよぎる。
「流二は……ずっと気付いてたの?」
あたしは小さい声でそう呟いた。
「え?」
あたしがそう言うと、流二はあたしから離れた。
「ずっと、気付いてたの?あたしが強がっ……「当たり前だろ?俺を誰だと思ってんだよ」
あたしが言おうとした言葉を、流二が遮った。
そして、少し寂しそうな顔をして更に続けた。
「お前が強がってることくらい……最初から分かってたよ」
流二は声のトーンを低くしてそう呟くと、あたしの隣りに座った。
「……えっ」
あたしの目にはまた出るハズのない涙が浮かんだ
「頼むから……もう一人で抱え込むのやめろよ。俺が居るんだから、ちゃんと言えよ」
流二は小さな声でそう言うと、あたしをギュッと抱き締めた。
その瞬間、あたしの目から大粒の涙が溢れた。
「ごめんなさい。……本当に、ごめんなさい」
あたしはそう呟くと、流二の腕から滑り落ちて床に座り込み、泣き崩れた
いくら泣いても止まらない涙。
いくら拭ったって溢れ出てくる。
もう、どうしようもないんだ。
あたしは、流二に辛い思いをさせていたんだ。
……苦しめていたんだ。
あたしは申し訳ない気持ちと、嬉しい気持ちが―――…
だから、みんなの居ない所で声を押し殺して泣いていたんだ。
授業中だってそうだった
教科書で顔を隠しては、下を向いて泣いた。
それは自分自身が一番よく分かってた。
イケないことなんだって
……分かってたつもりだった。
けど一人で抱え込んで、その気持ちを誰にも話す訳でもなくて、胸の中にそっとしまい込んできた
それがイケなかったんだ
それが逆に……流二を苦しめていたなんて、全然分からなかった。
もし誰かに相談していたら……ちょっとは変わっていたのかな?
全てを打ち明けていたら……こんなに辛い思いをしなくて済んだのかな?
今更だけど、そんな考えが頭をよぎる。
「流二は……ずっと気付いてたの?」
あたしは小さい声でそう呟いた。
「え?」
あたしがそう言うと、流二はあたしから離れた。
「ずっと、気付いてたの?あたしが強がっ……「当たり前だろ?俺を誰だと思ってんだよ」
あたしが言おうとした言葉を、流二が遮った。
そして、少し寂しそうな顔をして更に続けた。
「お前が強がってることくらい……最初から分かってたよ」
流二は声のトーンを低くしてそう呟くと、あたしの隣りに座った。
「……えっ」
あたしの目にはまた出るハズのない涙が浮かんだ
「頼むから……もう一人で抱え込むのやめろよ。俺が居るんだから、ちゃんと言えよ」
流二は小さな声でそう言うと、あたしをギュッと抱き締めた。
その瞬間、あたしの目から大粒の涙が溢れた。
「ごめんなさい。……本当に、ごめんなさい」
あたしはそう呟くと、流二の腕から滑り落ちて床に座り込み、泣き崩れた
いくら泣いても止まらない涙。
いくら拭ったって溢れ出てくる。
もう、どうしようもないんだ。
あたしは、流二に辛い思いをさせていたんだ。
……苦しめていたんだ。
あたしは申し訳ない気持ちと、嬉しい気持ちが―――…