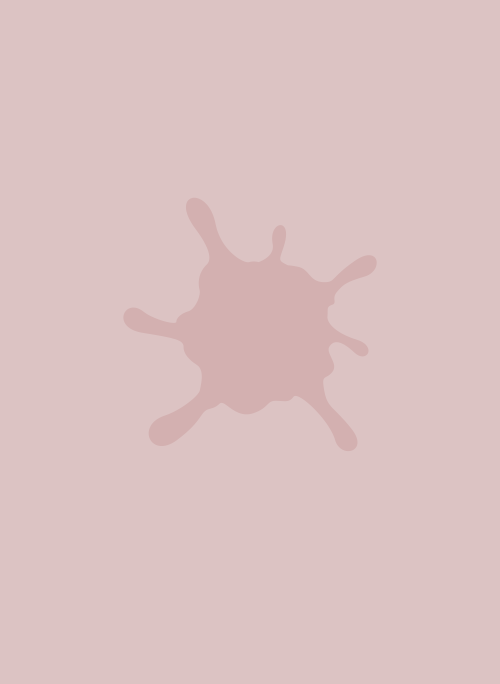雨上がりの道路は、太陽の光を反射してキラキラと輝いていた。
朝倉に借りたタオルでサドルと荷台を拭く。
ハンドルを握り、サドルにまたがる僕。
「乗っていいよ」
日よけの下に佇む唯にそう言うと、彼女はおもむろに荷台に腰掛けた。
僕の肩を掴む感触が懐かしかった。
「じゃあ、お願いします」
お願いします、か。
敬語か。
そうだよね、僕たちはもう他人だもんね。
ペダルに足をかけ、ゆっくりと漕ぎ出す。
最初は重かったが、加速度を帯びるにつれて、だんだんスピードが上がっていく。
風を作ってしまえ、いつの間にか流れていた涙が乾くように。
涙?
紛れもない涙だ。
別に何か期待してるわけじゃない。
なのに、涙が止まらないのは何故なんだ?
プライドなんてクソくらえだ。
自転車に翼が生えて、時空を超えて、僕たちが一緒に過ごしたあの日々まで、飛んでいけたらいいのに。
ーひとっ飛び・終わりー
朝倉に借りたタオルでサドルと荷台を拭く。
ハンドルを握り、サドルにまたがる僕。
「乗っていいよ」
日よけの下に佇む唯にそう言うと、彼女はおもむろに荷台に腰掛けた。
僕の肩を掴む感触が懐かしかった。
「じゃあ、お願いします」
お願いします、か。
敬語か。
そうだよね、僕たちはもう他人だもんね。
ペダルに足をかけ、ゆっくりと漕ぎ出す。
最初は重かったが、加速度を帯びるにつれて、だんだんスピードが上がっていく。
風を作ってしまえ、いつの間にか流れていた涙が乾くように。
涙?
紛れもない涙だ。
別に何か期待してるわけじゃない。
なのに、涙が止まらないのは何故なんだ?
プライドなんてクソくらえだ。
自転車に翼が生えて、時空を超えて、僕たちが一緒に過ごしたあの日々まで、飛んでいけたらいいのに。
ーひとっ飛び・終わりー