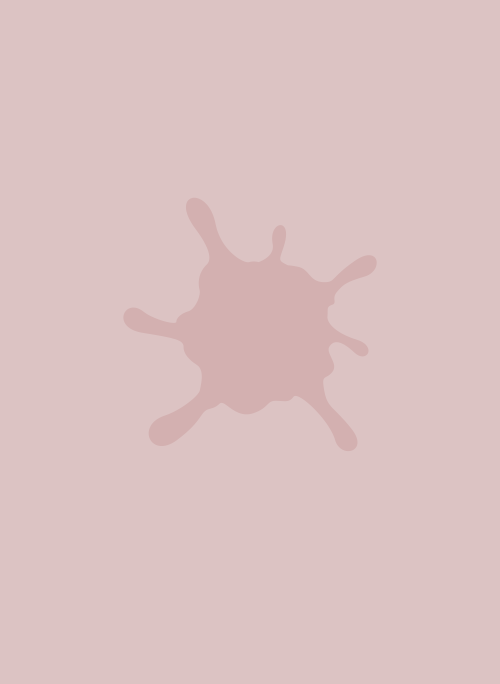ドアが開く気配を感じ、僕たちは慌てて体を離した。
ひょっこり顔を出したのは朝倉だった。幸運だったと言っていい、先輩たちに見つかっていたら、大目玉を食らっていただろう。
言い訳するまでもなく、朝倉は、僕と宮原唯の間に誕生した関係を察知したようだった。
不自然に頬を掻きながら、彼はドアを締めてどこかへ行ってしまった。
僕と唯は顔を見合わせて、クスリと笑った。
吹奏楽部のホルンの演奏が、僕らの呼吸音を消していた。
ひょっこり顔を出したのは朝倉だった。幸運だったと言っていい、先輩たちに見つかっていたら、大目玉を食らっていただろう。
言い訳するまでもなく、朝倉は、僕と宮原唯の間に誕生した関係を察知したようだった。
不自然に頬を掻きながら、彼はドアを締めてどこかへ行ってしまった。
僕と唯は顔を見合わせて、クスリと笑った。
吹奏楽部のホルンの演奏が、僕らの呼吸音を消していた。