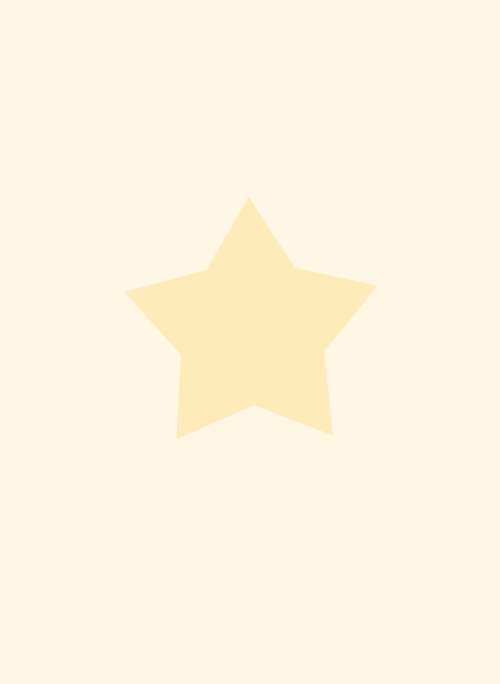自転車のペダルに足をかけたまま、ちょっと背伸びをして塀の奥を覗き見る。
綺麗に刈り込まれた芝生の庭の向こう側。
大きな窓のその奥。
そこに、曲に合わせて風にそよぐ草木のように身体を揺らす彼女の姿があった。
ただはっきりとその顔を確認することは出来ない。
なぜなら彼女と僕との間には窓とは別に、視線を拒むような、白い白いレースのカーテンが引かれていたからだ。
かろうじて全体の姿かたち、髪の長さはわかるけれど──
──どんな瞳をしていて
──どんな唇をしていて
──どんな肌の白さで
──どんな指の細さで
──どんな声で笑うのか……
そこまではわからない。
そう。
だから彼女は『レース越しの君』。
決してこの手の届かぬ場所に咲く、高嶺の花。
踏み入れることの叶わぬ異国に住む、深窓の令嬢。
肉まん片手の僕とは“どえらく”世界の違う人なのだろう。
この場所に立っているのは、たまたま。
本当なら、出逢うことのなんて一生なかったんじゃないだろうか。