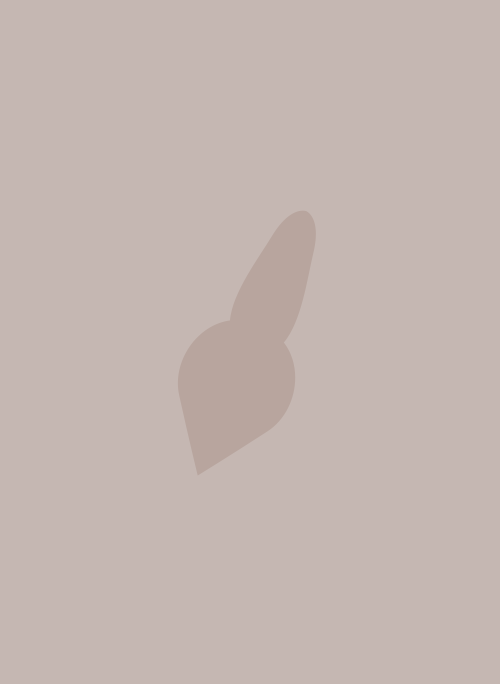「じゃあ、なんで今も、さっきも泣きそうな顔してんだよ。」
真剣な顔の旭の瞳に戸惑った自分が映っているのが見えた気がした。
「…泣きそうなんかじゃない。」
「嘘つくな。俺が気づかないと思ってんのかよ。」
段々、眉間に皺がよっていき少し怒り始めた旭。
こうゆう時の旭は
恐いけど、優しい。
…そんな旭に
私は頼って、いいのか?
今までのように
甘えてしまって、いいのか?
…そんなの、
前と変わらないじゃない。
「…旭…、眉間に皺よってる。」
「あ?」
突拍子もないことを言った私に、旭は少し腕の力を緩めた。
その隙に、掴まれていた腕をほどいた。
「ちょっ、おい!詩依良っ…」
「大丈夫、だから。」
驚く旭はそう言った私を見て押し黙った。
「何でもないから。…大丈夫。」
目を合わさないように、おやすみと呟くと、旭に背を向けて自分の部屋の方に走りだした。
旭が何か呟いていたけど聞こえなかった。
いや、聞こうとしなかった。
だって…、
聞いたら甘えてしまうから。
これでいいかなんて分からない。
でも、こうしなきゃいけない気がしたんだよ。
「…ッ、大丈夫なんて顔してねぇじゃねぇか…。馬鹿やろう…。」
たとえ、
旭が私の嘘に気づいていようとも
私は、
こうしなきゃいけない気がしたんだよ。