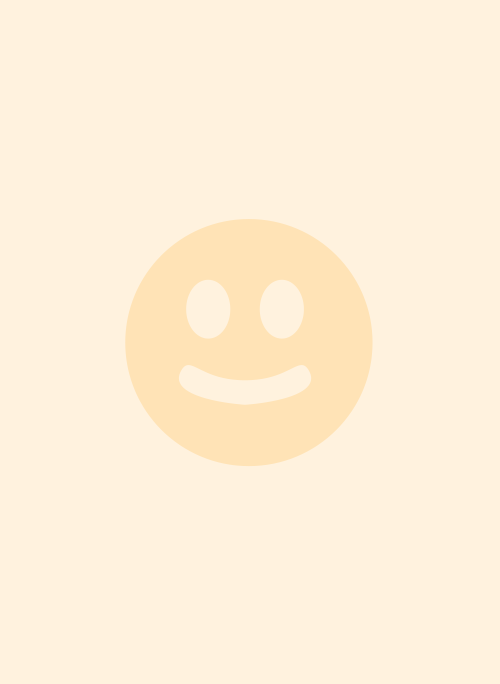その日の放課後。
ホームルームでなぜか任命され、今日がこの学校最後の神崎さんに花束を渡した。
「ありがとう」
複雑な拍手の中、はにかんだ彼女はなぜか懐かしい気がする。
神崎さんとなにかあったっけ?
彼女がやってきてから、この一月に言葉を交わしたのは数回のはず。
頭をひねるけど、そのたびになぜか気だるい頭痛がした。
その体調不良は初めてのはずなのに、心の奥では「まただ……」と嘆いていた。
「……神崎さん…」
「媚薬」
何を言っていいかわからなくて、彼女の名を口にした瞬間だった。
小さな呟きが、わたしの耳に届く。
「え?」
「…あなたには、もう必要ないはずよ?」
神崎さんが何を言っているかわからなくて、「はあ……」とやっぱり曖昧にしか返事が出来なかった。
もう一度ペコリとお辞儀をした彼女の後姿をわたしはただ、じっと追いかけていた。
バイトだという百合と愛美は早々に下校して、一人で帰り道を歩く。
相変わらず女の子のはしゃぐ声と共に、遠くで翔くんの声がした。
つい先日、わたしに声をかけてきたくせに…
と思いつつも、彼が彼なりの幸せがあるのならばいいか、と納得していた。
いつもの帰路に不定期に行われるフリマ。
所狭しと洋服やアクセサリーを中心に並んでいる。
こういうのは嫌いではなく、お財布も寂しいことだし、人の間からチラチラとのぞきこんでいた。
ホームルームでなぜか任命され、今日がこの学校最後の神崎さんに花束を渡した。
「ありがとう」
複雑な拍手の中、はにかんだ彼女はなぜか懐かしい気がする。
神崎さんとなにかあったっけ?
彼女がやってきてから、この一月に言葉を交わしたのは数回のはず。
頭をひねるけど、そのたびになぜか気だるい頭痛がした。
その体調不良は初めてのはずなのに、心の奥では「まただ……」と嘆いていた。
「……神崎さん…」
「媚薬」
何を言っていいかわからなくて、彼女の名を口にした瞬間だった。
小さな呟きが、わたしの耳に届く。
「え?」
「…あなたには、もう必要ないはずよ?」
神崎さんが何を言っているかわからなくて、「はあ……」とやっぱり曖昧にしか返事が出来なかった。
もう一度ペコリとお辞儀をした彼女の後姿をわたしはただ、じっと追いかけていた。
バイトだという百合と愛美は早々に下校して、一人で帰り道を歩く。
相変わらず女の子のはしゃぐ声と共に、遠くで翔くんの声がした。
つい先日、わたしに声をかけてきたくせに…
と思いつつも、彼が彼なりの幸せがあるのならばいいか、と納得していた。
いつもの帰路に不定期に行われるフリマ。
所狭しと洋服やアクセサリーを中心に並んでいる。
こういうのは嫌いではなく、お財布も寂しいことだし、人の間からチラチラとのぞきこんでいた。