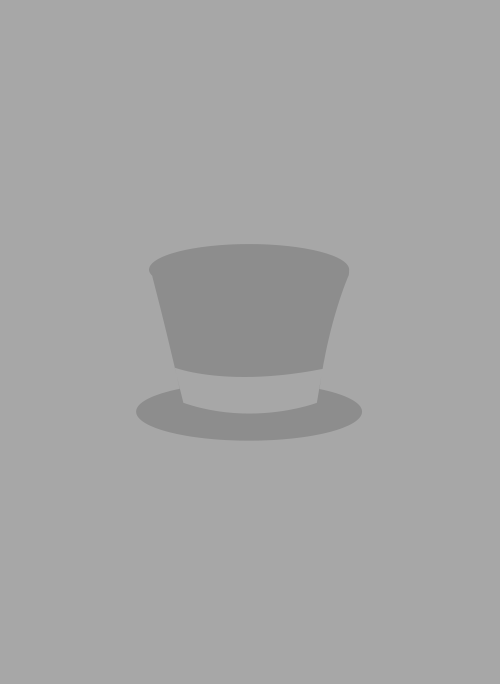俺は、自分を恥じた。
ルシルはかわいそうな女の子なんかじゃない。
かわいそうなのは、こんな風に人を上から見下ろしている俺の心だ。
どうしてルシルは、いつもいつも、こんなに俺の心を暖かくしてくれるんだろう。
俺は、無意識にルシルの肩をそっと抱き寄せた。
母のしごきに耐えてくれなんて言う必要、全然なかった。
彼女は、それでさえ、新しくて楽しい経験だって、さらっと言ってのけるのだから。
俺は今更ながら、ルシルの強さを目の当たりにして、心が震えた。
きっと母は、こういうルシルのことを、俺なんかよりずっと深く理解して、気に入ったんだろうな。
ほんの数日でルシルを気に入った母の慧眼には、頭が下がるばかりだ。
「あ、あの・・マーズレン?」
ルシルの恥ずかしそうな声に、俺は、自分のしていることに気付いた。
「わゎっ!ご、ごめん!ルシル!」
俺が慌てて腕を離すと、真っ赤になったルシルが恥ずかしそうに視線を逸らした。
体中の血液が、一気に顔に集中した俺の顔も、多分彼女以上に赤い顔をしているに違いない。
俺は、何度もルシルに謝りながら、彼女の部屋を後にした。
なにやってんだ、俺。