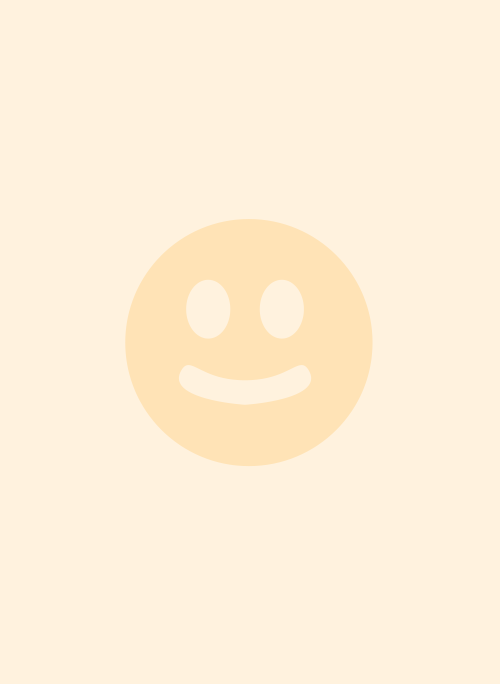「俺が調べられた限りではそんなモンだ。後は流石に…昔の事件を掘り返しすぎると上に文句言われるからな」
「いや…充分助かるよ…有り難う」
芳三は苦笑するが、楡は至って真剣に答えた。
手元にある封筒は分厚く、芳三が仕事の合間を縫って、手間暇掛けて調べ上げてくれたに違いない。
そう思うと、自分が巻き込んだことに対して、文句一つ言わない彼の態度に頭が下がる思いだった。
適当にパラパラと捲り、ある1ページに目が留まる。
「これ…」
「…ん?」
「この吉成隆(よしなりたかし)って、コイツの知り合い?」
芳三はコーヒーを飲んでから、楡の指差す部分を覗き込む。
「あぁ、そうらしい。学生時代の親友だそうだ。今は鑑識やってるよ。…何だ、珍しいな。おまえがそんなに一生懸命になるなんてさ。なんか思い入れでもあんのか?」
「……………」
思い入れ……
そう言われれば、無いと答えては嘘になる。
しかし、思い入れとはまた違った感情であることも事実で、楡は返答に困った。
元々口数が多い方では無いので、こういった状況の時は困ってしまうことが多かった。