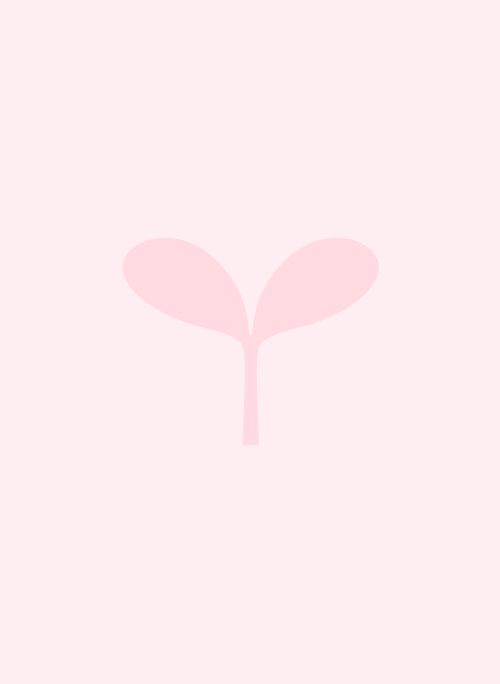僕は最初、ケベックシティに向かうつもりだった。「彼女」が最後に絵はがきを寄こした場所だからだ。
雲を掴むような、とはよく言ったもので、僕にはそれ以外に何の手掛かりも持ち合わせていなかった。
だけど、「そこには居ないわ」とシロナは首を振った。実にはっきりと。
「じゃあどこに?」
と僕が眉を寄せると、今度は力なく首を横に振った。
彼女は全知全能ではない。むしろ知らないことの方がはるかに多いようだった。
それでも僕はシロナの助言どおり、カナダ行きを思いとどまった。
――ロンドンへ。
それが僕達の答えだった。
雲を掴むような、とはよく言ったもので、僕にはそれ以外に何の手掛かりも持ち合わせていなかった。
だけど、「そこには居ないわ」とシロナは首を振った。実にはっきりと。
「じゃあどこに?」
と僕が眉を寄せると、今度は力なく首を横に振った。
彼女は全知全能ではない。むしろ知らないことの方がはるかに多いようだった。
それでも僕はシロナの助言どおり、カナダ行きを思いとどまった。
――ロンドンへ。
それが僕達の答えだった。