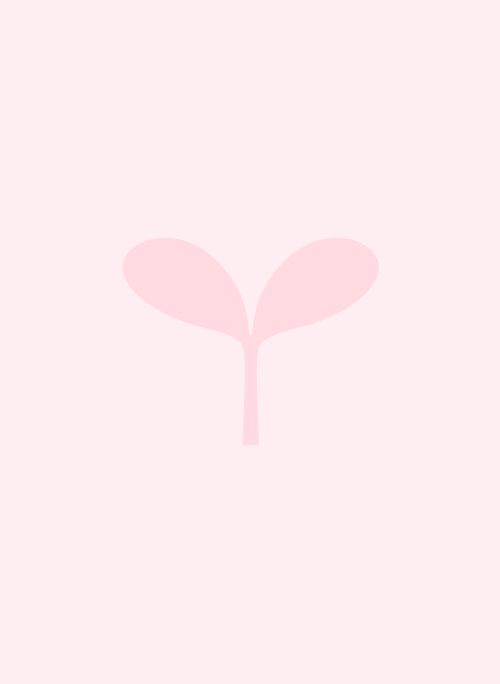僕は明け方のテラスで瞳をつむり、早紀のことを思い起こしていた。
凛と冷えた空気に、低い鳩の鳴き声だけが溶け込んでいく。
瞼の奥で、永遠にセーラー服を着たままの早紀が立っていた。
僕はもうずっと長い間、心の奥底に鍵をかけて生きてきた。だから、こんなに心が乱れるのは初めてだった。
シロナの所為だろうか?
それとも年を取った証拠なのだろうか?
瞼の奥に立つ早紀の顔は、十年という時の流れの中でいつしか輪郭がぼやけていた。
それでも、彼女が微笑んでいることだけは分かった。
目を開くと、それまで見えていた早紀の姿が砂粒のように消えた。
そして、シロナが立っていた。
「迎えに来たの?」
と僕が訊ねると、シロナは黙ったまま白くて繊細な指先を伸ばし、僕の頬を撫でた。
「シロナ」
シルクのように心地よい感触の中で、僕はもう一度訊ねた。
「そうよ」と彼女は言った。
気がつくと、僕の頬を撫でていた彼女の指先が濡れていて、はじめて僕は泣いていたんだと気が付いた。
凛と冷えた空気に、低い鳩の鳴き声だけが溶け込んでいく。
瞼の奥で、永遠にセーラー服を着たままの早紀が立っていた。
僕はもうずっと長い間、心の奥底に鍵をかけて生きてきた。だから、こんなに心が乱れるのは初めてだった。
シロナの所為だろうか?
それとも年を取った証拠なのだろうか?
瞼の奥に立つ早紀の顔は、十年という時の流れの中でいつしか輪郭がぼやけていた。
それでも、彼女が微笑んでいることだけは分かった。
目を開くと、それまで見えていた早紀の姿が砂粒のように消えた。
そして、シロナが立っていた。
「迎えに来たの?」
と僕が訊ねると、シロナは黙ったまま白くて繊細な指先を伸ばし、僕の頬を撫でた。
「シロナ」
シルクのように心地よい感触の中で、僕はもう一度訊ねた。
「そうよ」と彼女は言った。
気がつくと、僕の頬を撫でていた彼女の指先が濡れていて、はじめて僕は泣いていたんだと気が付いた。