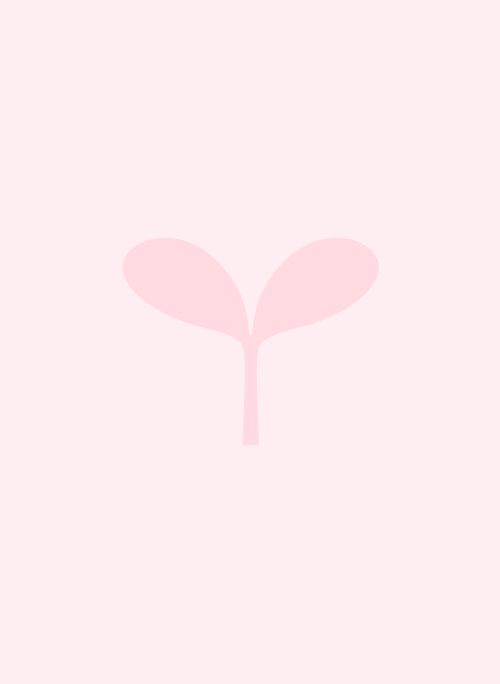とにかくすべてがそんな調子だった。
すべてが惰性と倦怠の中で泡つぶのように流れていく。
僕はその気泡をただじっと海の底から眺めている。
耳を澄まし、見えるはずもない淡く揺れる水面を、ただじっと。
クジラの歌声が聞こえる。
早紀の声が聞こえる。
部屋の重力が反転する。
魂が空に浮かぶ。
そしてまた、僕は眠る。
朝が来る。
歌を聴く。
僕はまだ生きている。
この十年とはつまり、僕にとってそういう十年だった。
意味があるのか、ないのか、そもそも意味を問うことすら馬鹿らしいような蒼一色の海の底を、僕は黙々と泳ぎ続けていた。
すべてが惰性と倦怠の中で泡つぶのように流れていく。
僕はその気泡をただじっと海の底から眺めている。
耳を澄まし、見えるはずもない淡く揺れる水面を、ただじっと。
クジラの歌声が聞こえる。
早紀の声が聞こえる。
部屋の重力が反転する。
魂が空に浮かぶ。
そしてまた、僕は眠る。
朝が来る。
歌を聴く。
僕はまだ生きている。
この十年とはつまり、僕にとってそういう十年だった。
意味があるのか、ないのか、そもそも意味を問うことすら馬鹿らしいような蒼一色の海の底を、僕は黙々と泳ぎ続けていた。