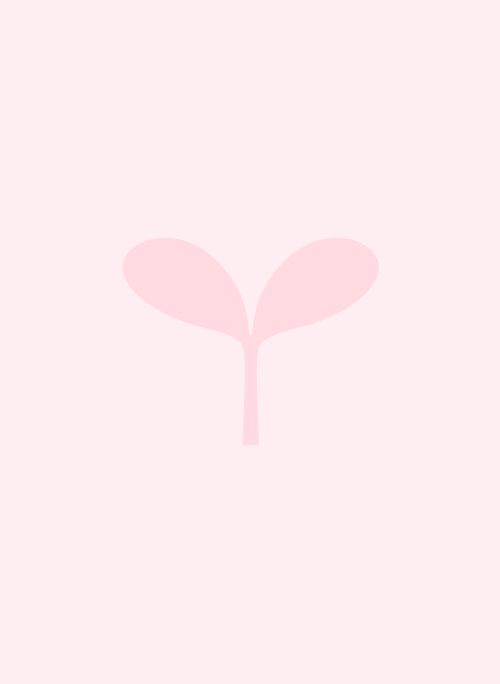僕は車両の一番後ろの壁に掛けられている時計を見た。
中間地点のヨークまで、まだ幾らも列車は走っていなかった。
いつしか僕は眠っていた。
ビロード張りの背もたれに体を預け、まどろみに溶け込んでいく感覚は、僕の五感を心地よく弛緩させた。
時折目を覚ますと、向かいに居るはずのシロナの姿が消えていた。
とは言え、存在そのものが消えたという感覚ではなくて、彼女の息づかいだけはいつも近くに感じられた。
実際、次に目を覚ますと、シロナはちゃんと側にいた。
ある時は向かいに腰掛け、ある時は僕の肩に頬を乗せて。
僕は再び目を閉じた。
一定のリズムで揺れ続ける車内に、穏やかな午後の陽射しが差込んでいた。
側で微かな吐息を感じた。
彼女もまた、静かな寝息をたてて眠っているようだった。
中間地点のヨークまで、まだ幾らも列車は走っていなかった。
いつしか僕は眠っていた。
ビロード張りの背もたれに体を預け、まどろみに溶け込んでいく感覚は、僕の五感を心地よく弛緩させた。
時折目を覚ますと、向かいに居るはずのシロナの姿が消えていた。
とは言え、存在そのものが消えたという感覚ではなくて、彼女の息づかいだけはいつも近くに感じられた。
実際、次に目を覚ますと、シロナはちゃんと側にいた。
ある時は向かいに腰掛け、ある時は僕の肩に頬を乗せて。
僕は再び目を閉じた。
一定のリズムで揺れ続ける車内に、穏やかな午後の陽射しが差込んでいた。
側で微かな吐息を感じた。
彼女もまた、静かな寝息をたてて眠っているようだった。