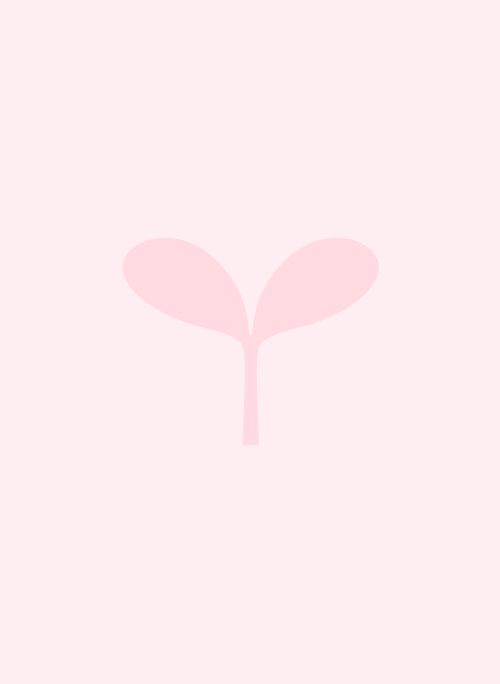なぜ?なぜ?……と、僕の頭の中をいろんな疑問が渦巻いていた。
ただ一つ明らかなことは、この思考の迷宮から逃れるには、旅を続ける以外にないということだった。
窓の外を見ると、列車はゆるりと弧を描きながら、草原の中を走っていた。
草原、羊、草原、草原、そして街。街を出ると再び草原……
ヨークまでの風景は、ずっとそんな感じで続いていた。
「まるで緑色の天の川を走る銀河鉄道にでも乗り込んだ気分ね」
列車の窓にもたれ掛かりながら、シロナがあくびをかみ殺した。
「宮沢賢治は知ってるんだ」
「ええ」
「夏目漱石は知らないのに?」
「そうみたいね」
シロナはペロリと舌を出した。
「草原はもう飽きた?」
「ちょっとね」
それから「羊は?」と尋ねると、「とっくに」と言って彼女は笑った。
ただ一つ明らかなことは、この思考の迷宮から逃れるには、旅を続ける以外にないということだった。
窓の外を見ると、列車はゆるりと弧を描きながら、草原の中を走っていた。
草原、羊、草原、草原、そして街。街を出ると再び草原……
ヨークまでの風景は、ずっとそんな感じで続いていた。
「まるで緑色の天の川を走る銀河鉄道にでも乗り込んだ気分ね」
列車の窓にもたれ掛かりながら、シロナがあくびをかみ殺した。
「宮沢賢治は知ってるんだ」
「ええ」
「夏目漱石は知らないのに?」
「そうみたいね」
シロナはペロリと舌を出した。
「草原はもう飽きた?」
「ちょっとね」
それから「羊は?」と尋ねると、「とっくに」と言って彼女は笑った。