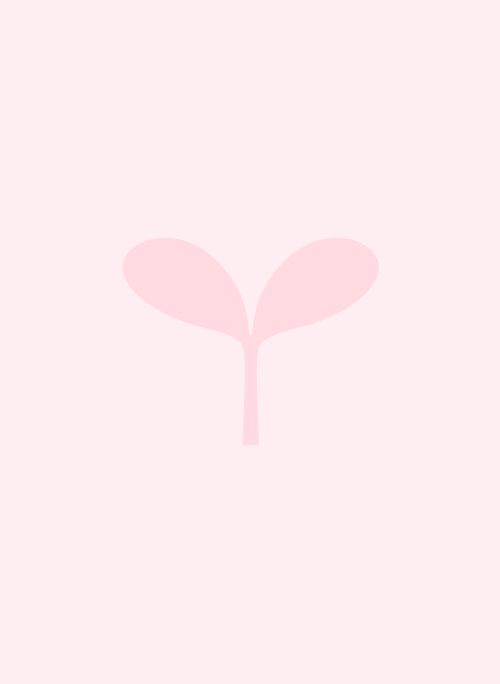教室で誰かが笑っていた。
眩しい夏の陽射しの中を、入道雲がせり出していた。
先生の声が聞こえた。
僕は一人、窓の外の虹を見ていた。
たった一度しかない十五歳の夏が始まろうとしていた。
カーテンが揺れた。
バキッとシャーペンの芯が折れた。
折れた芯は虚空を彷徨い、板張りの床に音もなく落ちた。
その忌まわしき記憶は、十年経った今でも必ずシャーペンの芯で終わる。
眩しい夏の陽射しの中を、入道雲がせり出していた。
先生の声が聞こえた。
僕は一人、窓の外の虹を見ていた。
たった一度しかない十五歳の夏が始まろうとしていた。
カーテンが揺れた。
バキッとシャーペンの芯が折れた。
折れた芯は虚空を彷徨い、板張りの床に音もなく落ちた。
その忌まわしき記憶は、十年経った今でも必ずシャーペンの芯で終わる。